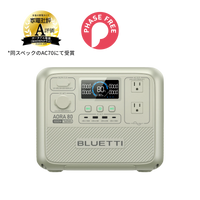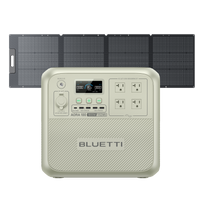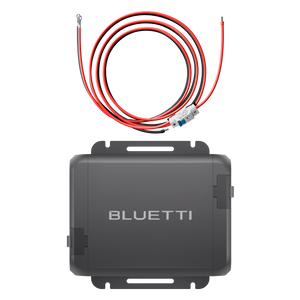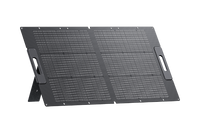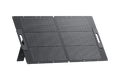地震の前に現れると噂される「地震雲」。本当に前兆なのか、ただの自然現象現象なのか不安に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では、地震雲の科学的見解や過去の事例、間違えやすい気象現象をわかりやすく整理しました。そのうえで、家庭で実践できる防災対策や停電時に役立つ備えも紹介しています。確実な地震予知はできなくても、備えによって安心は手に入れられます。
地震雲とは?
地震雲という言葉は多くの人が耳にしたことがありますが、実際にどのようなものなのでしょうか。ここでは一般的に言われる特徴や、科学的な見解を整理します。
定義と特徴(気象庁の見解)
地震雲とは、地震が起こる前に空に現れるとされる特異な形をした雲を指します。帯のように長く伸びたものや細い筋のようなもの、あるいは渦を巻いたような形状など、日常ではあまり目にしない姿をしているのが特徴とされます。
ただし気象庁の見解によれば、地震と雲の形には科学的な因果関係は確認されていません。雲の生成は大気中の水蒸気や気圧、気温などの気象条件によって左右され、地下で起こる地震の前兆とは直結しないと説明されています。
結論として、「地震雲」と呼ばれる現象の多くは人々が思い込みで関連づけたものであり、科学的根拠はないといえるでしょう。
地震雲と間違えられる10種類の雲 ❘ その種類と特徴とは?
空に広がる雲には多彩な姿があり、気象条件によってその形や現れる高さが異なります。ここでは地震雲と間違えられる代表的な雲の種類を順を追って紹介します。
【上層雲:高度5~13km付近によく見られる】
・①巻雲(けんうん)

出典:気象庁
最も高い位置に出現する雲のひとつで、白く細い繊維のような外観が特徴です。鳥の羽や絹糸を思わせる姿をもち、すじ雲とも呼ばれます。温暖前線や低気圧の接近に伴い、空に現れることがあります。
・②巻積雲(けんせきうん)

出典:気象庁
小さな白い雲が規則正しく並び、小石を敷き詰めたようにも、さざ波のようにも見える雲です。個々の雲は離れている場合が多いものの、つながって広がることもあります。うろこ雲やいわし雲という呼び名でも知られ、温暖前線や低気圧が迫るとき、巻雲のあとに姿を見せます。
・③巻層雲(けんそううん)

出典:気象庁
淡く白いベールのように広がる雲で、空の大部分を覆うことがあります。日差しを通すため地面には影ができ、太陽や月を覆うと光の輪「暈(かさ)」が現れるのが特徴です。前線や低気圧が近づく際に出やすい雲とされています。
【中層雲:高度2~7km付近によく出現】
・④高積雲(こうせきうん)

出典:気象庁
白または灰色の小さな雲が比較的規則正しく並び、モザイク模様や帯状、レンズのような形をつくります。ときには塔のように立ち上がる姿を見せることもあります。巻積雲と似ていますが、より低い位置に現れ、影を持ち、雲のかたまりも大きいのが相違点です。別名「まだら雲」や「ひつじ雲」とも呼ばれます。
・⑤高層雲(こうそううん)

出典:気象庁
灰色や青みがかった層状の雲で、広い範囲の空を覆います。薄い部分を太陽が通ると、すりガラス越しに見るようにぼんやりと確認できます。厚みを増した高層雲は雨を降らせることもあり、温暖前線や低気圧が接近する際に見られる雲です。巻雲や巻積雲の後に現れるのが特徴とされています。
・⑥乱層雲(らんそううん)

出典:気象庁
低く厚い灰色の雲が空を覆い、太陽を完全に隠してしまいます。前線や低気圧の中心部で発達し、本格的な雨を降らせる雲として知られています。空全体を重苦しく覆い尽くすのが大きな特徴です。
【下層雲:地上付近~2kmに多く見られるが、積雲や積乱雲の頂は中層や上層に達することもある】
・⑦層積雲(そうせきうん)

出典:気象庁
灰色や白っぽい色をした雲で、大きなかたまりがモザイク模様や丸い塊、ロール状となって空に広がります。雲同士がくっついたり離れたりするのが特徴で、雨を降らせることはあまり多くありません。
・⑧層雲(そううん)

出典:気象庁
雲の中で最も低い位置にできる灰色の雲で、ときに霧雨をもたらすことがあります。地表にまで達すると霧となり、太陽が透けて見える場合は輪郭がはっきり確認できるのが特徴です。
・⑨積雲(せきうん)

出典:気象庁
ちぎった綿のような姿をしており、輪郭が明瞭で密度が高い雲です。四季を通じて現れますが、特に晴れた日に見られることが多いです。太陽に照らされた部分は明るく輝きますが、底は平らでやや暗く見えます。積雲が成長して雄大積雲になるとカリフラワー状の頂をもち、強い雨を伴うこともあります。
・⑩積乱雲(せきらんうん)

出典:気象庁
雄大積雲がさらに発達したもので、非常に濃い密度をもち底は暗く重たい雲です。頂は成層圏に届かず、対流圏の境界で横に広がり、かなとこの形をした「かなとこ雲」として知られます。雷雲や入道雲とも呼ばれ、豪雨・雷・突風・ひょうを伴い、ときに竜巻を引き起こすため注意が必要です。
過去に地震雲が報告された3つの事例
地震雲には科学的な裏付けはありませんが、過去には地震の直前に目撃されたとの報告もあります。そのため、完全に存在を否定するのは難しいといえるでしょう。ここでは、地震雲が現れたと伝えられる代表的な地震を取り上げます。
事例①福井地震ー1948年
「地震雲」という言葉を広めたとされる鍵田忠三郎は、この地震の2日前に地震雲を観測し、予知していたと伝えられています。福井平野を震源とするマグニチュード7.1の大地震で、被害は甚大でした。住家の全壊は34,000棟を超え、犠牲者は3,769人に及びます。
参考:内閣府
事例②阪神淡路大震災ー1995年
淡路島北部を震源としたマグニチュード7.3の阪神・淡路大震災も、地震雲が観測されたと報告される代表的な事例です。発生の約1週間前、1995年1月9日の夕刻に震源近くの明石海峡大橋上空で、竜巻のように渦を巻いた地震雲が撮影されました。
その後も地震雲に関する体験談が数多くインターネット上で語られましたが、信頼性が高いとは言えないものがほとんどでした。証言全体の中では、およそ4割以上が地震雲に関連する内容だったとされています。
参考:Newsポストセブン
事例③トルコ・シリア大地震ー2023年
5万9,000人を超える犠牲者を出したトルコ・シリア大地震の前にも、地震雲とされる雲が目撃されたとの報告がありました(※6)。2023年1月19日、トルコ西部ブルサの上空で複数層が重なった奇妙な形状の雲が撮影され、SNSを通じて「地震雲」として急速に拡散しました。
ところが気象学の専門家によれば、それは「つるし雲」と呼ばれる現象で、山を越える空気の流れによって発生するものです。つるし雲はメカニズムが既に解明されており、地震とは一切関係がないと説明されています。
参考:NHK
地震雲と誤認されやすい7つの気象現象
「地震雲だ」と話題になる雲の多くは、実際にはすでに知られている気象現象で説明できるものです。ここでは、地震雲とよく混同される典型的な雲の例を見ていきます。
①飛行機雲や竜巻雲

縦に長く伸びる雲は「地震雲ではないか」と誤解されることが最も多いケースです。ところが、実際には次のような現象によって生じます。
- 飛行機雲:航空機のエンジンから放出された水蒸気が氷結して筋状に残る
- 積乱雲の初期段階:大気の不安定さによって縦に成長する雲
- 竜巻の形成過程:強い上昇気流が生み出す筋状の雲
これらはいずれも気象条件や物理現象によるもので、地震そのものとは無関係です。
②うろこ雲

うろこ雲は高積雲(アルトクムルス)の一種で、魚のうろこや水面の波紋のように規則的な模様を描く雲です。正式名称は「高積雲列(アルトクムルス・ウンドゥラトゥス)」と呼ばれます。
- 形は魚のうろこや波紋に似た整ったパターン
- 主に気圧の谷や寒冷前線が近づくときに出現
この雲は天候の変化を知らせるサインであり、地震の前兆ではありません。
③放射線雲

放射線雲は、細長い帯状の雲が平行に並び、遠近法の影響で地上からは一点から放射しているように見える現象です。幻想的で少し不気味にも感じられるため、特別な雲と誤解されがちです。
しかし実際は光学的効果による見え方に過ぎず、「巻雲」や「積雲」など一般的な雲でも起こる現象です。したがって、地震活動とは全く関係がありません。
④波状雲

波状雲はその名の通り、波のようにうねる形をした雲で、大気の層が異なる速度で流れるときに生じる空気の波動によって作られます。見た目が不気味に映るため、地震雲と誤解されることも少なくありません。
しかし実際には、大気の乱流や風の動きを映し出しているだけであり、地震活動との関わりは一切ありません。
⑤断層雲

断層雲は雲が途中で鋭く切り取られたように見える現象で、空に断層が走ったように見えることから地震との関連を疑われがちです。けれども、その正体は次のように説明できます。
- 正体:異なる気流がぶつかる境界線
- 発生条件:気温や湿度が急に変わる大気の境界面
- 観測されやすい場面:前線の通過時や山岳の風下側
つまり断層雲は、地震の前触れではなく局地的な気象条件の変化によって生じる現象です。特に前線が通過するときに出現することが多く、天気の変化を予測する手がかりにもなります。
⑥吊るし雲

吊るし雲は、山などの高地を越える風がつくり出す山岳波によって形成される雲の一種です。同じく山の存在が要因となる「笠雲」と同じカテゴリーに含まれます。
地形が高ければ高いほど風は強く上昇しやすく、その結果雲が発生します。そのため富士山をはじめとした標高の高い山の周辺で多く見られる雲です。
⑦太陽柱

太陽柱は雲ではなく、空気中に浮かぶ氷の結晶に太陽光が反射して生じる光学的な現象です。その独特な姿から「地震雲」と誤解されることがあります。
この現象は気温が低く、六角形の氷晶が漂っているときに現れやすく、特に日の出や日の入りといった冷え込みやすい時間帯に観察されます。夜間でも月明かりによって同じような現象が見られる場合があります。
太陽柱は光の反射や屈折によって起こるものであり、地震活動との関連はまったくありません。寒冷地や冬の時期に多く確認されることからも、気象条件による自然現象であると理解できます。
地震の前兆とされる8つの現象
地震雲は科学的な裏付けがないため、地震との直接的なつながりはほぼ否定されています。とはいえ、いまだ解明されていない自然現象の中には地震の予兆と考えられるものも存在します。ここでは代表的な例を取り上げて解説します。
①地鳴り
地鳴りとは、地震の前や地震中に地下の岩盤が動くことで生じ、その振動が音として伝わる現象です。特徴や仕組みは次のとおりです。
- 音の特徴:低く響く轟音や遠雷のような音
- 発生の仕組み:岩盤のずれや破壊による振動が音波となって地表に届く
- 予兆としての信頼性:科学的な裏付けはなく、多くは体感による証言
「地震の直前に地鳴りを聞いた」とする声は多いものの、科学的に明確に解明されたわけではありません。ただし、東北大学東北アジア研究センターの石渡明氏は、本震の揺れ(S波)に先立って到達する初期微動(P波)が音として感じられる可能性を指摘しており、全くの否定はできないとしています。
参考:東北大学
②井戸水や温泉水の異常
地震の前触れとして、井戸水や温泉の水量・温度・色・匂いに変化が見られることがあります。地殻変動によって地下水脈に影響が及び、その結果として水質や状態に変化が生じると考えられています。
実際に、1975年の中国・海城地震の際にも井戸水の異常が報告されました。ただし、この現象は地域差が大きく、すべての地震で起きるわけではありません。さらに、2025年現在でも科学的な裏付けは確認されていないのが実情です。
③動植物の異常
地震の直前に動物が落ち着きを失ったり、普段と異なる行動をとる事例が報告されることがあります。人には感じ取れない環境の微妙な変化を、動物が敏感に察知している可能性があるのです。
代表的な異常行動の例:
- 犬や猫が吠えたり鳴いたりし、室内飼育でも外へ出たがる
- 鳥が普段と異なる時間に鳴き出す、群れで異常な飛行をする
- 魚が水面に浮かぶ、跳ねる、あるいは岸に打ち上げられる
- 昆虫が集団で移動したり、季節外れに姿を見せる
ただし、これらは「地震の前後に偶然起きた可能性」を排除して証明するのが難しく、信頼性の高い地震予知の方法としては確立されていません。あくまで関連性が指摘されている現象のひとつに過ぎないといえます。
④発光現象
地震の前後に空に光が走る現象が観察されることがあり、「地震光」と呼ばれる特殊な発光現象として知られています。大地震の際に目撃された事例が複数報告されています。
代表的な発光現象の種類:
- 光の柱:青や白の光が地上から天に向かって伸びる
- 閃光:強烈な光が一瞬だけ空を照らす
- 光球:球状の発光体が空中に浮かぶ
- オーロラ状の光:空全体が波打つように輝く
これらは岩石が圧縮・摩擦されることで生じる圧電現象(高電圧の発生)や、地中からのガス放出に伴う発光によって説明されることがあります。阪神・淡路大震災(1995年)やペルー地震(2007年)でも目撃例が報告されていますが、科学的なデータは十分ではなく、仕組みは未解明です。
参考:京都産業大学
⑤異常な赤い朝焼け・夕焼け
異常なほど赤く染まる朝焼けや夕焼けも、地震の前兆ではないかと語られる現象です。実際に、2011年の東日本大震災の直前には宮城県で通常よりも濃い赤色の朝焼けが確認されました。
そもそも朝焼けや夕焼けが赤く見えるのは、太陽光に含まれる短波長の青い光が大気中の塵によって散乱し、長波長の赤い光だけが地上に届くためです。
⑥高層大気の電離層で電子数の増加
2024年、京都大学の研究チームは大地震直前に電離圏で観測される電子数の異常が物理的に説明できると発表しました。
プレート境界の粘土層に含まれる水は、地震発生前に高温高圧のもとで超臨界状態となり、電磁気学的な異常を引き起こすとされています。実際に2016年の熊本地震では、発生直前に電離層上空で電子数の急増が観測されました。
参考:京都大学
⑦巨大地震に先駆けて起きる前震
本震の数日から数カ月前に震源域で発生する小規模な地震は「前震」と呼ばれ、大地震の前兆として注目されます。ただし、前震の段階でそれを本震の予兆と断定することは難しく、前震が起こらずに本震と余震だけが続くケースも存在します。
2016年の熊本地震では、震度7の本震の2日前に同じく震度7の前震が発生しました。本震と同規模の前震が観測された極めて珍しい事例として記録されています。
参考:内閣府
⑧深海魚が上がってくる
普段は海の深部に生息し、人の目に触れることがほとんどない深海魚。突然「網に掛かった」と聞くと、不吉な出来事の前触れではないかと感じてしまう人も少なくありません。しかし、深海魚と地震の関係については「東海大学海洋研究所」と「静岡県立大学」の研究チームが調査を行い、迷信であると結論づけています。調査では、深海魚の漂着・捕獲事例と、そこから1,000km以内でマグニチュード6以上の地震が発生した回数を比較しました。
その結果、約83年間にわたる336例のうち、深海魚が見つかった後に実際に地震が起きたのはわずか1件のみ。したがって、深海魚が上がったとしても慌てる必要はなく、地震の前兆とみなす根拠はありません。
関連人気記事:大地震の前兆はある?過去の実例と防災対策を紹介
災害時の「偽情報」や「誤情報」に注意 ❘ 正しい防災意識3選
災害が発生すると多くの人が不安に陥り、SNSなどを通じて根拠のないうわさや偽情報が一気に広がりやすくなります。そのため、「災害時には必ず流布するもの」と理解し、情報の正確性を落ち着いて確認する姿勢が欠かせません。
①災害時は“偽情報”や“誤情報”が拡散する事を知る
兵庫県立大学の木村玲欧教授によれば、災害直後は「理解できないことが起きた」「再び発生するのでは」という不安感や、「状況を知りたい」という切実な思いが多くの人に共有されます。これが背景となり、偽情報や誤情報、デマや根拠のないうわさが通常より拡散しやすくなると指摘しています。
さらに、過去の大規模災害でも同じようなデマが繰り返し広がっていたことから、特に災害直後に流れてくる情報には注意が必要です。教授は「その内容に触れたときには、必ず冷静に真偽を見極めてほしい」と呼びかけています。
②特に広まりやすいのは「原因予想」「再来予想」「偽被害の状況」
地震のケースでは、災害直後に原因を憶測したり再来を予言したりする根拠のないうわさが特に拡散しやすい傾向にあります。
過去の大規模地震では「人工地震が原因だ」「○月に再び大地震が来る」などの言説が広まりました。実際に2024年1月の能登半島地震でも、「人工地震が起きた」という主張や、東日本大震災の津波映像を「今回の津波」と偽って拡散する例がSNSで相次ぎました。
さらに、被害情報が伝わり始めると、事実ではない情報や二次被害を煽るデマが急速に広がります。代表例としては、虚偽の救助要請や「被災地で窃盗団が活動している」といった偽情報が挙げられます。こうした誤情報は救助活動を妨げ、命に直結するリスクを招きかねません。
③立ち止まり、冷静な情報確認をする
災害直後は「また起きるのでは」「状況を把握したい」という不安から、感情を刺激する情報をつい拡散してしまう傾向があります。
そのため、「大規模災害では根拠のないうわさや誤情報が必ず出回る」と認識し、共有する前に一度立ち止まって冷静に確認する姿勢が大切です。信頼できる発信元かどうかを確認したうえで判断するように心がけましょう。
今すぐ取り組める地震対策6選
地震を正確に予知する仕組みはまだ確立されておらず、発生のタイミングを事前に特定することは困難です。だからこそ、「いつ起きても備えがある状態にしておくこと」こそが最大の防御策です。ここでは家庭で今すぐ実践できる、命を守るための具体的な対策を紹介します。
対策①家具の固定と配置を見直す

地震による人的被害の多くは、家具の転倒や落下によって生じる事故です。安全を高めるためには、家具の固定と配置を工夫することが欠かせません。
- 背の高い家具はL字金具や突っ張り棒で壁にしっかり固定する
- 寝室や出入口付近には倒れやすい家具を置かない
- ガラス部分には飛散防止フィルムを貼って割れても安全を確保する
- 重いものは必ず下段に収納する
特に家具の配置を見直すだけなら費用をかけずにできるため、今すぐにでも取り組める対策といえるでしょう。
対策②生活必需品を備蓄しておく

大規模な地震が起きると、電気・ガス・水道といったライフラインが途絶える可能性があります。そのため、最低3日分、できれば7日分の生活必需品を準備しておくことが望ましいです。備えておくべきものは以下のとおりです。
- 水:1人あたり1日3リットルを目安に、人数×日数分
- 食料:火を使わず食べられる保存性の高いもの
- 衛生用品:トイレットペーパー、ウェットティッシュ、マスクなど
- 医薬品:常備薬、消毒液、絆創膏などの応急処置用品
- 生活用品:懐中電灯、乾電池、携帯ラジオ、モバイル充電器
これらの備蓄品は定期的に確認し、賞味期限や使用期限をチェックすることが大切です。普段の生活で少しずつ使いながら補充していく「ローリングストック法」を取り入れると、無理なく備えを継続できます。
関連人気記事:非常食を賢く選んで、災害に備える
対策③非常持ち出し袋を備える

大規模な地震が起きるとライフラインが止まり、避難が必要になることがあります。その際に役立つのが非常持ち出し袋の準備です。最低限の生活を維持できるよう、必要なものをまとめておきましょう。
- 飲料水や保存食(少なくとも3日分を目安に)
- 懐中電灯や予備電池
- 携帯電話の充電器やモバイルバッテリー
- 救急セット、常備薬、マスク
- 防寒具や下着、タオル
これらは家族構成や健康状態に応じて調整してください。準備さえ整えておけば、いざという時に慌てず行動できます。
対策④避難経路と避難場所の確認

地震発生時には、まず安全に避難できる経路を把握しておくことが命を守る鍵となります。普段から自宅や職場、学校から避難所までのルートを確認し、障害物や危険箇所がないか点検しておきましょう。
- 家族全員で避難経路を共有しておく
- 夜間や停電時でも移動できるよう懐中電灯を用意する
- 通学路や通勤路に危険な場所がないか確認する
- 避難所だけでなく一時的な集合場所も決めておく
これらを事前に確認しておけば、災害時に慌てず迅速に行動できるようになります。
対策⑤家族での安否確認方法を決めておく
大規模な地震では通信回線が混雑し、連絡が取りづらくなることがあります。そのため、家族全員で安否確認の手段や集合場所を事前に決めておくことが大切です。
- 災害用伝言ダイヤル(171)や各キャリアの災害用伝言板を利用する
- SNSやチャットアプリなど、複数の連絡手段を準備しておく
- 集合場所をあらかじめ設定し、誰もが分かるように共有する
- 遠方の親戚や知人を連絡の中継役にする方法も有効
こうした取り決めをしておけば、連絡がつかない状況でも安心感を得られるでしょう。
対策⑥停電対策にポータブル電源を準備
大規模地震の後には長期間の停電が発生する可能性があります。そのため、家庭で活用できる電源や照明の備えが欠かせません。
・BLUETTI AORA 30 V2(288Wh)|軽量設計で停電時にも頼れる電源

アウトドアから停電対策まで幅広く役立つ、フェーズフリー仕様のポータブル電源です。AORA 30 V2は288Whの容量を備えながら片手で持ち運べる軽量設計で、場所を選ばず使えるのが特長。USBやACポートを搭載しており、スマホやLEDライト、扇風機など複数の機器を同時にカバーします。
キャンプや車中泊を快適にしてくれるのはもちろん、停電時には緊急電源として真価を発揮します。利用目安は携帯電話で約16回充電、ノートPCで約4回使用、電気毛布なら約3.5時間、LEDライトで約24.6時間、扇風機は約5.5時間と実用的です。
平常時も非常時も活躍できる頼れる相棒として、暮らしに取り入れておくと安心感がぐっと高まるでしょう。
・BLUETTI AORA 100 V2(1024Wh)❘ 万能性能で停電時も暮らしを守る電源

AORA 100 V2は容量1024Whを誇るポータブル電源で、11.5kgのコンパクトサイズながら家庭をしっかり支える万能モデルです。平常時はキャンプやアウトドアで小型クーラーボックスや調理家電を稼働させ、停電時には冷蔵庫や炊飯器といった生活家電を安定して動かせます。静音設計のため屋内でも快適に使用でき、AC・DC・USBすべてに対応。長時間の電力供給を可能にし、停電時でも安心して暮らしを続けられる点が大きな強みです。
利用目安はスマホで約52回分、ノートPCで約12.6回分、Wi-Fiルーターで約46時間、炊飯器で約1.4時間、LEDライトで約52時間、電気ケトルで約1.6時間と実用性は十分。
「日常の便利さ」と「非常時の安心」を兼ね備えたフェーズフリーな一台として、家庭に常備しておく価値の高いモデルといえるでしょう。
FAQ
地震前に地震雲が現れるという話を耳にしますが、本当なのでしょうか?
地震研究者の間では、雲と地震に直接的な関係はないという見解が一般的です。過去には「地震の前兆としての雲」に関する研究が発表されたこともありますが、それによって雲と地震の関連性が確立されたわけではありません。
むしろ、大地震の直前にたまたま特異な形の雲を目撃し、それを地震と結びつけてしまった事例が多いと考えられています。逆に地震が発生しなかった場合、その雲の存在は人々の記憶から忘れ去られるケースがほとんどです。つまり「地震雲」の多くは偶然を関連付けているに過ぎない、というのが現時点での見方です。
一番怖い雲は何ですか?
一般的には、「積乱雲(せきらんうん)」が最も恐れられています。積乱雲は雷や豪雨、突風、ひょう、竜巻などの極端な気象現象を引き起こす原因になります。
特に「かなとこ雲」と呼ばれる積乱雲の発達した形は、大気が非常に不安定になっている証拠で、災害級の天候をもたらす可能性があります。地震雲と誤解されることもありますが、地震とは無関係で、大気の不安定な状態によって形成されます。これらの雲を確認した際は、屋内に避難し、気象情報をこまめにチェックしてください。
日本で1番やばい地震はいつですか?
日本で最も被害が大きかった地震として、1923年の関東大震災(マグニチュード7.9)が歴史的に知られています。死者・行方不明者約10万5千人、建物全壊約10万9千棟という甚大な被害を記録しました。近年では、2011年の東日本大震災(マグニチュード9.0)も死者・行方不明者約2万2千人、津波による壊滅的な被害で深刻な影響を及ぼしました。
まとめ
地震雲は科学的な根拠に乏しく、前兆と断定することはできません。しかし、地鳴りや動植物の異常、電離層の変化など、研究途上の現象も存在します。確実にできる備えは、日常からの防災対策と停電への備えです。家具の固定や備蓄、ポータブル電源の準備を整えておけば、いざという時にも落ち着いて行動できます。今日から一歩ずつ備えを進め、安心できる暮らしを築きましょう。
この記事から商品を購入する
関連記事
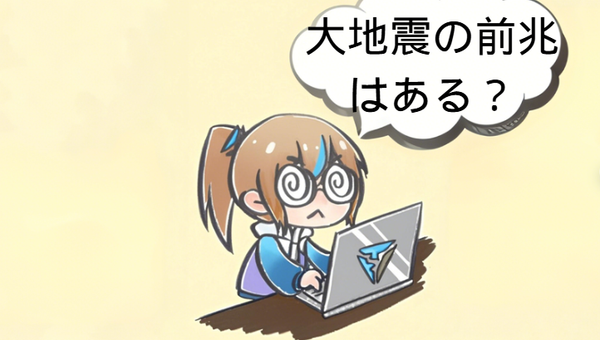
不安を抱えつつも「備えあれば憂いなし」と考えたい大地震への準備。本記事では、過去の地震の実例や警戒すべき前兆、私たちが日常生活でできる具体的な防災対策を徹底解説。見慣れない現象や小さな揺れが続くとき、未来の安心のために何をすべきかがわかります。

大切なテレビが地震で倒れると、怪我や損傷など思わぬ被害を引き起こす可能性があります。適切な転倒防止グッズや設置方法を知ることで、安心・安全な住環境を整えませんか?本記事では、手軽に実践できる防止策や、大型テレビも守れる対策をご紹介します。賃貸でもできる方法も必見です!

災害への備え、できていますか?家族を守るための非常食をスーパーで気軽に揃える方法を徹底解説!缶詰やレトルト食品、乾物まで、普段の買い物の延長で始められる防災備蓄術を詳しくご紹介します。初心者でも簡単に取り入れられるコツが満載です。