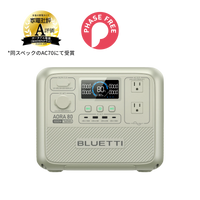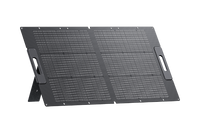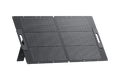最近、小さな地震が増えているけど「これって大地震の前兆なの?」と不安を感じていませんか?本記事では「大地震の前兆」をテーマに、前震の仕組みや過去の事例、電磁気異常や地盤変動などの予兆、そして日頃からできる防災対策までを詳しく解説します。地震に備えて今すぐできる行動を知りたい方に役立つ内容をお届けします。
精度の高い予測は困難でも、地震の前兆は「存在する」

最初にお伝えしたいのは、現代の科学では地震の正確な日時を予測することは不可能ということ。しかし過去の事例から、ある種の異常が地震と関連している可能性があることが示唆されています。
「大地震 前兆」というキーワードで検索する人が多い背景には、「少しでも早めに大地震を予測できたら避難しやすいのに」という切実な願いがあるはずです。
特に、大規模な地震が起きる可能性の高い地域では、科学的に地震の前兆に関する研究が進められており、「地震の前兆と思われるできごと」についても一定の確実性があると言われています。
ただし、現代の科学をもってしても「○月×日に大地震が来る」と断定することはできません。その理由は、地震が発生するメカニズムが非常に複雑だからです。
それでも「大きな地震の前に前兆があった」という体験談や観測例があることも、また事実です。なかでも比較的知られているのが「前震」と呼ばれる小さな地震が頻繁に起こるケース。
以下では、前震について具体的に解説し、それがどのように大地震のシグナルとして語られているのかを紹介します。
小さい地震が頻発すると要注意?「前震」とは

「前震(ぜんしん)」とは、大きな地震(本震)の前に頻発するやや小規模な揺れを指します。気象庁や地震学の分野では「本震が起こった後から振り返って見たとき、同じ震源付近で起きた小さな地震のこと」と定義づけるのが一般的です。この前震は、本震の直前に起きることもあれば、1ヶ月以上前に起きることもあり、パターンは一定ではありません。
さらに、一番最初の揺れが前震ではなく本震そのものである可能性もあるのです。
そのため、「これは前震だ!」とリアルタイムで断定するのはほぼ不可能に近いわけですが、複数回の小さな地震が立て続けに観測されるとき、研究者や防災の専門家は警戒レベルを上げる場合があります。
-
地震の種類の違い
|
前震 |
本震よりも先に起きる小さな地震。地震の前兆の可能性があり、より大きな地震へ警戒を引き締める必要がある。 |
|
本震 |
一定の期間や領域内で発生する地震活動において、最も規模が大きい地震 |
|
余震 |
本震が起きた後に断層のずれや歪みが再調整される過程で起こる地震 |
前震の段階で大地震の発生を完璧に予測するのは難しいですが、「最近やけに同じ地域で小規模の地震が増えているな…」と感じたら、防災対策を再点検してみる価値は十分あるでしょう。
ここからは、前震の代表的な事例として語られる3つの地震について見ていきます。
大地震の前に連発した前震の事例3選
前震を捉えて本震を事前に予測できたという明確な実績は、これまでにはありません。ただし、過去の大規模地震を振り返ると、前震とみられる小さな揺れが本震よりも先に起きている例はいくつも確認されています。
以下では、近年発生した震度7の巨大地震を事例としてご紹介します。
能登半島地震(2024年1月1日)
2024年の元旦に、石川県輪島市・志賀町付近を震源とした能登半島地震が起きました。マグニチュード7.6、最大震度7を観測した巨大地震による住宅の倒壊や土砂崩れにより、死者260名、重軽傷者1,323名という深刻な被害を出し、約4万4千戸が停電の影響を受けました。実は2024年1月の本震の前から、数年にわたって能登群発地震と呼ばれる小中規模の地震が頻発していました。なんと、2020年12月以降〜2023年末までに最大震度1以上の地震を506回観測していたのです。
さらに、この地震の能登群発地震マグニチュード5.5の前震が観測されたのは本震のわずか4分前。元日で帰省者が多かったこともあり、前震後すぐに本震が襲ったことで、人的被害の規模が一気に拡大してしまいました。
熊本地震(2016年4月16日)

2016年4月16日に熊本県で発生した熊本地震では、最大震度7という猛烈な揺れを記録しました。人的被害は2,957名に及び、約21万棟の住宅が損壊、さらに約47万戸が停電しています。熊本県益城町で記録された揺れの規模は計測震度で6.7を示し、東北地方太平洋沖地震の際に宮城県栗原市で計測された震度6.6を超え、日本の観測史上で最も激しい揺れとして記録されました。
マグニチュード7.3の本震に先駆けて、2日前の4月14日に発生したマグニチュード6.5の前震を皮切りに計7回にわたって前震が発生しています。この前震自体が一部地域では震度7に達したため、多くの人が「14日の地震を本震と思っていたら、実はそれが前震だった」という体験をしました。このケースでは、前震と本震の間が約28時間という短いスパンであったため、大きな被害が集中したともいわれます。
東日本大震災(2011年3月11日)
東日本大震災は2011年3月11日に三陸沖を震源として発生し、戦後最悪の自然災害となりました。この地震で1万9,775名が死亡し、行方不明者も2,550名に達したほか、約466万戸が停電しました。
この地震の2日前である2011年3月9日にも三陸沖を震源としたマグニチュード7.3(最大震度5弱)の地震が観測されており、また1日前の3月10日にもマグニチュード6.8(最大震度4)の地震が観測されました。これらの揺れは後に前震だったと判明しています。マグニチュード7クラスの地震自体が非常に大きな揺れですが、それをさらに上回る大地震が数日後に来るとは、多くの人が想定していなかったのも事実です。
“前震”の他にもある?大地震の前兆かもしれない5つのサインとは

出展:NHKニュース
震度7に達する可能性が高い「南海トラフ」巨大地震は、今後30年以内に発生する確率が当初の「70%から80%」から「80%程度」(2025年1月1日時点)へと引き上げられました。そのため、多くの方が家族の安全を守るためにも、地震が起きる前の兆候を知りたいと考えるでしょう。前震はわかりやすい前兆の一つですが、それ以外にも「これは大地震のサインかもしれない」と言われる現象がいくつかあります。ここでは代表的なものを5つ取り上げてみましょう。注意:これらの現象は観測されていますが、地震を予測することが科学的に証明されていません。
1. 地鳴りが発生する
地盤が振動して生じる「地鳴り」もまた、地震の前兆として挙げられる現象です。地鳴りは地震の発生時刻とほぼ同時に起こるものと考えられ、揺れが来る直前あるいは同時に耳に入ります。
地震の揺れには、初期に到達する横波(P波)、その後の強い揺れである縦波(S波)、そして海底で音に変換されるT波という3つがあります。これらはP波→S波→T波の順に現れ、最初に到達するP波が地鳴りとして人間の耳に届き、その直後にS波が大きな揺れをもたらします。
2. 電離圏の電子数異常が起こる
過去の大規模な地震の際、上空の電離圏において電子数が異常に変化することが確認されています。実際、2011年の東日本大震災でも、本震・前震・余震それぞれの発生20〜30分前に電離圏電子数の異常が観測され、1995年1月17日の阪神淡路大震災では、地震の約2週間前から数時間前までの期間に、「ラジオやテレビで雑音が入った」「リモコンや携帯電話が誤作動した」などの報告が地震後に多数寄せられています。
この分野の研究は今も継続中のため、現時点で科学的に確立した地震予知法とはいえません。ただ、京都大学が2024年4月に電離層異常を引き起こす物理的な仕組みを特定したと発表しており、今後さらに検証が進めば地震予知への道が開ける可能性もあります。
3. 海面の急激な変動が見られる(潮が引くなど)
日本の近海では潮の干満差が小さいため、海面の急激な変動が地震の前兆とされる場合があります。過去には地元の漁師や住民が地震に伴う地盤の上下変動を目撃するケースが存在します。例えば1927年に起きた丹後地震では、3月7日18時28分の本震が発生する数時間前、これまで一度も見たことがなかった岩が海面に姿を現しました。この時の地盤の隆起は約1メートルに達していたと推測されています。
4. 地盤のゆがみが変化する
地下の岩盤における僅かな歪みもまた、地震発生の前兆とされています。特に、今後30年以内の発生確率が高い南海トラフ地震では、地震発生の直前にプレート境界で岩盤が微妙にずれ動くことが指摘されています。日本では南海トラフ地震で大きな揺れが予測される静岡県、長野県、愛知県、三重県、和歌山県、高知県、愛媛県など39箇所に「ひずみ計」を設置し地盤の微細な隆起・沈降の変化を計測しています。
5. 井戸や温泉の水質・湧出量が激変する
地殻変動で地下水脈に影響が出ると、井戸水や温泉が突然濁ったり、湧出量が増減したり、温度が変化したりします。化学組成が変わる場合もあり、「硫黄のような匂いが強まる」という報告例も存在します。実際に1995年の阪神淡路大震災では、地震発生の数カ月前から六甲山地の地下水で湧出量が増え、塩素濃度などの化学的異常が観測されています。さらに1943年に起きた鳥取地震では、3月4日19時40分の地震の約30分前に、鳥取市内の吉方温泉で普段は透明だった温泉水が米のとぎ汁のように濁り、湧き出す量も通常の約1.5倍に増えたとの報告が上がっています。
小さい地震が相次ぐときにやっておくべき5つの対策
「小さな揺れが頻発してるけど、もしかしてこれってヤバいの…?」と不安になったときに、まず確認しておきたいのが防災対策です。家族や自分の生活を守るため、いくつかの基本ポイントを押さえておきましょう。
1. 家具の転倒防止を徹底する

地震の揺れによる人的被害の大きな原因の一つが「家具の転倒」です。東京都消防庁の資料によれば、地震によるけが人の約30〜50%が、家具の倒壊・落下・移動を原因としているというデータもあります。たとえけがをしなくても、倒れた家具が避難経路をふさいでしまえば、速やかに避難することが困難になります。以下のような転倒防止策を日常的に取り入れておきましょう。
- なるべく家具を生活空間に置かない
- L字型金具で家具を壁にしっかり固定する
- 重い物は低い棚に収納する
- 突っ張り棒で家具と天井の隙間を埋める
2. 日頃から避難経路と避難所を把握しておく
大規模な地震が起きた際には、行政から避難指示が出る可能性があります。その時に備え、あらかじめハザードマップを使って自宅周辺の避難所や避難ルートを確認しておくことが大切です。マップは市区町村のホームページから無料でダウンロードできるので、家族全員で目を通しておきましょう。
3. 住宅の耐震性を見直す

木造住宅にお住まいの場合は、耐震リフォームや耐震診断が必要かどうかをチェックしてみましょう。特に1981年以前に建てられた建物は旧耐震基準の対象であり、震度6強以上の大地震を想定していない設計が多いです。まずは専門業者に耐震診断を依頼し、必要に応じて改修工事を行いましょう。自治体によっては補助金制度を設けているところも多く、意外と費用負担を軽減できる場合があります。
4. 家族同士の安否確認の方法を話し合っておく
地震発生時に家族が一緒にいるとは限りません。バラバラの場所にいてもお互いの無事を確認できるよう、連絡手段をあらかじめ決めておくことが重要です。災害時には電話回線が混雑しやすいため、「災害用伝言ダイヤル(171)」など、回線負荷の少ない手段を活用することをおすすめします。また“第三者を通じた連絡手段”など、アナログや方法も検討しておきましょう。
5. 防災グッズは最低7日分以上用意する

地震が発生すれば、電気・ガス・水道・通信などのインフラが長時間にわたり使えなくなる恐れがあります。支援物資が届くまでのあいだを自力でしのげるよう、非常食や水、懐中電灯、ラジオ、簡易トイレなど、最低7日分の備蓄を心掛けてください。また高齢者や小さなお子様がいるご家庭では、衛生用品や常備薬、専用の物資も忘れずに。以下は、準備が必要な防災グッズのリストです。
- 飲料水
- 保存が効く非常食
- 応急処置用の医療用品
- 充電可能なポータブル電源
- 現金(小銭を含む)
- 日頃から服用している薬類
- 衛生グッズ(マスク、生理用品など)
- 携帯型ラジオや手回し式ラジオ
地震への備えに最適なポータブル電源のおすすめ2選
大地震が発生すると、送電設備が損傷し、広範囲で停電が起きるリスクがあります。実際、地震による停電は3日以上続くことも珍しくなく、前震・本震・余震を含めれば、ある地域で何度も揺れが起こる可能性は十分に考えられます。つまり、いつ停電が発生してもおかしくないのが現実です。
そのような中で活躍するのが「ポータブル電源」です。これは大容量の電気を内部に蓄え、コンセントが使えない状況でもさまざまな電化製品へ電力を供給できる機器のことを指します。頻発する地震に備えてポータブル電源を用意する利点は、以下のとおりです。
- 夜に停電が起きてもLEDライトを使って周囲を照らせる
- エアコンや扇風機、電気毛布を稼働させて寒さ、暑さをしのげる
- 電気ケトルや電子レンジで温かい食事の調理が可能になる
- スマートフォンを充電して家族や友人と連絡を取り続けられる
- 冷蔵庫を動かして食品を腐らせずに保管できる
- 携帯ラジオを使って最新の災害情報を受け取れる
- 避難所へ持ち込めば、電気のある快適な環境が得られる
ただし、長引く停電の中では、ポータブル電源に貯めた電気だけでは足りなくなる可能性もあります。そんなときに力を発揮するのが「ソーラーパネル」との併用です。太陽光によってポータブル電源に継続的な充電が可能となれば、どれだけ長期間停電しても、必要な電力を自前で確保できます。ポータブル電源とソーラーパネルのセット製品として信頼されているのが、BLUETTI社の製品です。
BLUETTI AORA 100 大容量ポータブル電源 | 災害時にも日常と変わらぬ電力を
1時間の充電で1日分の電力が確保できる大容量モデル。地震の際には、AORA 100のUPS機能は停電をわずか20msで感知し、内部バッテリーから電源供給を開始します。最新リフト機能が電圧を調整することで、2700W以下の電熱製品(電気ポットやドライヤーなど)も使用可能に。
1,152Whの大容量なら、長期間の停電でもスマートフォンを最大58回充電し、停電時の光となるライトも88時間も使えます。長引く停電にも対応できるよう、太陽光ソーラーパネルでの充電も可能です。Charger 1と組み合わせて使えば、車で避難する間にも余剰電力を用いて充電ができ、避難先での電力を確保できます。
AORA80小型ポータブル電源:災害時に強いコンパクト設計
AORA80はよりコンパクトで軽量なモデル。最大2000Wの高出力機器にも対応できる「電力リフトモード」を搭載し、冷蔵庫や電気ケトルなど、災害時に最も必要な機器に安定した電力供給が可能です。スマートフォンの充電なら最大45回、扇風機は12.5時間、電気毛布は9.7時間と、地震の際にも体温を調整することができます。
地震によくある質問と答え
最後に、大地震の前兆や防災にまつわる、一般的によくある質問をまとめました。
Q: 地震雲には信頼できる根拠があるのでしょうか?
A: 昔から「地震雲を見た」という声は多いですが、科学的な裏付けは今のところ確認されていません。気象庁や専門家の多くは、それらの雲が他の気象現象との区別が難しく、統計的なデータも不十分であるとしています。不思議な雲を見かけた場合でも、防災情報をこまめにチェックする姿勢が大切です。
Q: 前震が発生したら大地震は必ず来るの?
A: 前震と思われる揺れが起きても、本震が続かない例は数多く報告されています。とはいえ、熊本地震のように「あとから前震だったと判明した」ケースも存在します。揺れを感じたら、しばらくは注意を緩めず警戒を続けるのが無難です。
Q: 地震速報はどこで確認できますか?
A: 地震速報を知る方法としては、テレビやラジオ、気象庁の公式サイトのほか、Yahoo!防災情報やNERVアプリなどの防災アプリが有効です。SNSの情報も流れますが、まずは信頼できる公式発表を確認するようにしましょう。
Q: 南海トラフで危険とされる県はどこですか?
A: 研究機関などの発表によると、静岡・高知・和歌山・三重・愛知などの沿岸地域がリスク上位に挙げられています。ただし、実際の危険度は地形や都市構造によって変わるため、ランキングにとらわれず、地域のハザードマップを活用することが重要です。
Q: 地震で最もリスクが高い県はどこでしょうか?
A: 「最も危ない県」を一概に断言するのは難しいのが現実です。震源の位置や活断層、沿岸の地形など多くの要素が影響します。全体で見れば、南海トラフ周辺から東北・関東沖にかけてが特に警戒すべきエリアです。ただ、日本全国にリスクは存在しています。
Q: 地震の予兆や予測は科学的にどの程度信頼できますか?
A: 現代の地震学では、日時や発生地点を事前に正確に特定することはできません。小規模な揺れや異常現象が観測されても、それが必ず大地震に結びつくとは限らないのです。ただし、異常な変化が見られた場合は専門機関が情報を発信するので、気象庁や自治体の発表を普段からチェックしておくことをおすすめします。
まとめ
地震の前兆は必ずしも明確ではありませんが、前震や地盤の変化、電磁気異常など、私たちが気づけるサインは存在します。大切なのは「備えておくこと」。日頃から対策を講じておけば、いざというときに家族を守る行動が取れます。今日からできる備えを、今すぐ始めてみませんか。あなたの準備が、未来の安心につながります。
この記事から商品を購入する
ニュースレターに登録
関連記事

もしも大阪に南海トラフ地震が起きたら、私たちはどう動けばいいのか?この記事では、想定される津波・揺れ・液状化・停電といった被害の全容と避難のタイミング、安全な避難場所の選び方までをわかりやすく解説。いざという時に命を守る準備、今すぐ始めませんか?

大きな揺れで食器棚が倒れたり、割れた食器が飛び散ったり…。そんなリスクから家族を守るために、いますぐできる地震&停電対策を徹底解説!日常の収納から非常時の備えまで、安全なキッチンづくりのコツをまとめました。

「家族や友人、社員と突然連絡が取れない!」そんな緊急事態でも慌てず対応するための安否確認方法を徹底解説!よくある原因の整理から、連絡が取れないときの適切な対処法、そして事前に備えるためのポイントまで、実用的な情報が満載です。