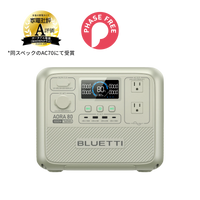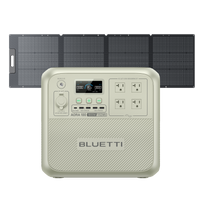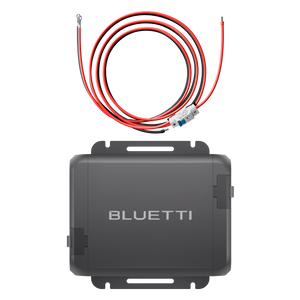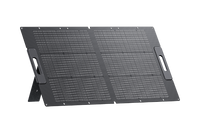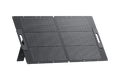「雷が落ちたら、実際なにが起こるの?」――音が近づくたび胸がざわつきますよね。被害は人の身体だけではありません。建物や配線、冷蔵庫や通信、生活のリズムにまで広がります。本稿は、屋外・屋内での具体策、家電を守るコツ、停電への準備を“いま手元で出来る順番”で並べました。あわせて、平常時と非常時を地続きにするフェーズフリーの考え方も短く触れます。普段から使い慣れた道具をそのまま非常時に回す。
雷が落ちたとき人のからだに起こること

- 直撃(ダイレクトヒット)
体そのものを電流が貫通します。心停止・呼吸停止・重度熱傷の危険が高く、最初の数分が勝負です。屋外では「開けた場所でいちばん高い存在にならない」。これだけで危険度を一段下げられます。長い傘や釣り竿、掲げたクラブ――これらで自分を“突起”にしないことが第一歩です。
- 側撃(サイドフラッシュ)
近くの高い物(木、鉄塔、柱)に落ちた電流が、弧を描いて人に飛び移る現象。木の下の雨宿りが危険と言われるのはここに理由があります。やむを得ずそばを通るなら、枝先から4m以上離れるのが目安です。
- 歩幅電圧(ステップ電圧)
落ちた電流は地表を這います。両足の間に電位差が生まれると、体内に電流が流れます。足を広げるほどリスクが上がるので、足を揃えてしゃがむ。地面に寝そべるのは逆効果です。
- 爆風・衝撃
落雷点の周囲では空気が急膨張し、衝撃波が生まれます。転倒、鼓膜の損傷、飛散物による怪我――電気以外の危険も現実的です。逃げ切れない場面では耳をふさぎ、頭を抱えて低姿勢でやり過ごしてください。
- 倒れた人を見つけたら
まずは周囲の安全を確認。次に呼吸と意識。必要ならただちに胸骨圧迫です。ためらいは禁物。AEDがあれば音声ガイダンスに従いましょう。雷は同じ場所に続けて落ちることもあります。二次被害を避けつつ、落ち着いて行動してください。
▼リスク別・対処早見表
|
シナリオ |
主な危険 |
NG行動 |
即やること |
|
直撃(ダイレクトヒット) |
心停止・重度熱傷 |
高い物を掲げる/開けた場所に立つ |
低姿勢で離脱→堅牢な建物か車内へ |
|
側撃(サイドフラッシュ) |
周辺高所からの飛び移り |
木の下で雨宿り |
枝先から4m以上離れる/高木や塔に近寄らない |
|
歩幅電圧(ステップ電圧) |
足元から体内へ通電 |
大股で走る・腹ばいになる |
足を揃えてしゃがむ/小幅で移動し安全範囲へ |
雷が落ちたとき建物や暮らしに起こること

人命に加え、雷は建物や車といった物理的環境にも深刻な影響を及ぼします。
- コンクリート・アスファルト
落雷点では爆裂や孔あきが起きることがあります。つい覗き込みたくなりますが、近寄らないのが正解。飛散物で怪我をします。
- 車(クルマ)
金属ボディが電流を外側へ逃がすファラデーケージの役割を果たします。基本的に車内は安全側。ただし完全停車して、ドア枠や窓枠など金属部から体を離しましょう。オープンカー、バイク、自転車では同等の保護は期待できません。
- 建物・配線・家電
電流は電気配線、アンテナ線、電話線、そして金属配管を通じて屋内に侵入します。家電の故障、ブレーカーの遮断、火災、停電――どれも珍しくありません。室内でも壁・天井・窓枠・金属配管・コンセントから1m以上離れておくと安心です。長時間の雷予報が出ている日は、モデムやルーター、テレビなどサージに弱い機器のプラグを抜く判断も有効です。
屋外で雷が近づいたときの行動ステップ

事前のアラート設定
気象庁「雷ナウキャスト」をブックマークし、アプリの通知をONにしておきます。
- 気象庁 雷ナウキャスト:https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/?contents=thunder
- Yahoo!天気アプリ(雷雨アラート対応):https://weather.yahoo.co.jp/weather/
- ウェザーニュースアプリ(落雷レーダー):https://weathernews.jp/
1. 堅牢な建物へ移動
鉄筋コンクリート造の学校・庁舎・図書館・駅ビル・商業施設、地下通路(浸水に注意)、道の駅など“金属骨格のある建物”が安全側です。木造の神社拝殿やプレハブ小屋、金属屋根だけの東屋は保護になりません。見当たらなければ車内(四輪・ドア閉)へ。オープンカーやバイクは不可。
〔農地・山間部の人へ〕
周囲に堅牢建物がない場合は、作業を中止し、ハウスや仮設小屋から離れて車内へ。金属支柱・柵・電気柵から4m以上離れ、トラクターは停めて降車(金属部から体を離す)。
2. “長いもの”を手放す
傘、釣り竿、旗竿、金属三脚。リュック外側の金属ペグも外します。
3. 木の下は近寄らない

側撃を避けるため、枝先から4m以上。孤立高木・鉄塔・アンテナ直下は特に危険。
4. 開けた場所を離れる
逃げ切れないときは保護範囲(高さ4〜20mの構造物の頂点が45°以上で見上げられる空間)に入り、足を揃えて低姿勢で待機。地面に寝るのは逆効果。
5. 距離の目安を簡単に
稲光から雷鳴までの秒数を数えると3秒≒1km。数字にこだわり過ぎず、少しでも近いと感じたら即退避。
6. 再開の合図は“静けさ+30分”
音がやんでも30分は待ちます。山の大会や野外イベントで使われる経験則です。
〔地域ごとの雷傾向メモ〕
日本海側は冬季雷が多く、内陸の山地は夏の午後に発雷しやすい傾向。東北は夏の局地的雷雨が増えやすく、活火山の周辺では噴火時に“火山雷”が観測されることもあります。旅や出張の前に土地勘をつけておくと判断が早くなります。
家の中に雷が落ちた場合の注意点(距離・水・コード)

- 距離をつくる
部屋の中央寄りに移動し、壁・天井・配管・窓・家電・コンセントから1m以上離れます。意外と触れてしまう金属棚や観葉植物の支柱も要注意。
- 水回りは使わない
入浴、洗髪、食器洗い、洗濯は落ち着いてから。水と金属配管は電気の通り道です。固定電話(有線)も受話器に触れるのは控えめに。
- コード類の扱い
使っていない機器は電源プラグを抜く。雷サージ対応タップや分電盤の避雷器(SPD)があれば、侵入電圧を和らげられます。ルーターやONUはサージに弱いので、予備機が一台あると復旧が早い。
- 子どもとペット
窓辺や金属ケージから離し、室内の中央へ。抱き上げるより、隣に寄り添って落ち着かせるほうが安全です。
〔子ども向けの合言葉〕
「壁・水・コードから一歩離れて まんなかへ」
「窓から1メートル」
「ピカッのあと 30分待つ」
小学生でも覚えやすい短い言い回しで、家族の合図にしておくと混乱が減ります。
停電リスクと“電気の備え”

落雷で送電設備や引込線が傷むと、数時間規模の停電が起きます。夜だと照明ゼロ、通信断、冷蔵の不安――一気に不便が押し寄せます。ここで効いてくるのがフェーズフリーの段取り。停電中でも重要な“通信”を維持するために、日常的にポータブル電源を活用することで非常時に慌てない備えになります。週末のベランダ作業、庭での団らん、勉強机の延長コード代わりに電源を使い込み、終わったら満充電へ。平時=練習、非常時=本番の感覚で回しておくと、いざ停電でも手が止まりません。
携帯性優先(個人・子ども部屋)
スマホ、LEDライト、小型ファンを1泊動かせる容量。片手で持ち上げて階段を昇れる重さが基準です。
家庭の基幹(家族・医療機器)
扇風機、CPAP、ルーター、タブレット学習など複数機器を同時に安定稼働できる出力と容量。リビングに“電源島”を一つ作るイメージで。
AORA 30 V2 ポータブル電源(約288Wh/定格600W)

AORA 30 V2は小型で、取り回しの良さが特徴です。LEDランタン(10W)×24時間、スマホ充電×数回、USBファン×16時間――“最初の一夜”の最低限がこれ一台で賄えます。寝室や子ども部屋へサッと運べるのも強み。
AORA 100 V2 ポータブル電源(約1,024Wh/定格1,800W)

AORA 100 V2は家庭全体の電力ニーズを支える中容量タイプです。扇風機、ルーター、学習端末、動画視聴、CPAPなど同時運用に余裕があります。リビングに置いておけば、停電時のストレスが目に見えて下がります。
運用のコツ
- 週末や日常的に活用し、使用後は必ず満充電にしておくことを習慣化しましょう。これにより、非常時でも迷いなく使えます。
- 重要な家電やデバイス(照明、通信機器、医療機器など)をリスト化し、実際にどの口に挿すか指示をポータブル電源に貼っておくと安心です。
- 冷蔵庫は開閉回数を抑えれば数時間は持つので、まずは照明と通信を確保して判断を急がない――これが結果的に食品ロスも減らします。
雷に関するよくある誤解と正しい知識
「背が高い人ほど落ちやすい?」
落ちやすいのは“周囲でいちばん高いもの”。背の高さそのものより、突起をつくらない立ち振る舞いが重要です。
「家の中なら100%安全?」
屋内は安全度が高いものの、配線・アンテナ・金属配管を通じて雷が入る余地は残ります。1m以上の距離と水回り回避を“作法”として身につけておきましょう。
「倒れている人に触れると感電する?」
触れても感電しません。体に電気が“溜まっている”わけではないので、呼吸と意識を確認し、必要なら胸骨圧迫とAEDをためらわずに。
「雷のときに電子機器を使うのは危険?」
充電中や有線接続中(壁のコンセントや有線LAN)での使用はサージの影響を受けやすいので控えます。電源から切り離したスマホやタブレットの操作そのものは一般に問題ありません。
「自分に落ちる確率が知りたい」
確率よりも、気づいたらすぐ避難の反射行動が命を守ります。稲光が途切れても30分は再開を待つ――この“余白”が安全を底上げします。
「ついやりがちなNG」
地面に腹ばい、木の下で雨宿り、金属フェンスにもたれる、高いものを掲げる。どれも側撃と歩幅電圧のリスクを上げます。やめておきましょう。
今日からできる雷対策ミニチェック
- 屋外:黒い雲、冷たい突風、稲光やゴロゴロ音――ピンと来たら中止→建物/車内へ。逃げ切れない時は保護範囲に入り、足を揃えて低姿勢。
- 屋内:壁・配管・コンセント・水回りから1m以上離れて待機。入浴や洗髪は雷が落ち着いてから。使っていない機器はプラグを抜く。
- 雷アラート:気象庁「雷ナウキャスト」をブックマークし、普段使いの天気アプリで“落雷”通知をONに。
└ 気象庁:https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/?contents=thunder
└ Yahoo!天気:https://weather.yahoo.co.jp/weather/
└ ウェザーニュース:https://weathernews.jp/
- 停電への備え:LEDヘッドライト、携帯ラジオ、モバイルバッテリーを手の届く場所に。BLUETTI AORA 30 V2 / 100 V2は平時から使い込み、家族で“どれをどこに挿すか”を共有(これがフェーズフリーの要)。
まとめ
雷の影響は、感電だけの話にとどまりません。建物・配線・家電・停電へ連鎖し、日常のリズムを簡単に崩します。外では高い物や開けた場所を避ける。室内では配線や金属から1m以上離れてください。また、稲光の後は30分余裕を持って行動しましょう。ほんの数手を事前に身体で覚えておくだけで、慌て方が変わります。
そして、フェーズフリーの電源を今日から。週末にポータブル電源を使い、その後は満充電にしておきましょう。停電時も灯りと通信を確保できることで、安全な対応を落ち着いて選択できるはずです。「雷が落ちた」ニュースに不安を覚えたら、家族で動線を一度歩いてみてください。ドアからどの部屋へ、どの電源へ――声を掛け合えば、それだけで備えは一歩進みます。最後は習慣の力です。慌てないための準備を、今日のうちに。
この記事から商品を購入する
ニュースレターに登録
関連記事
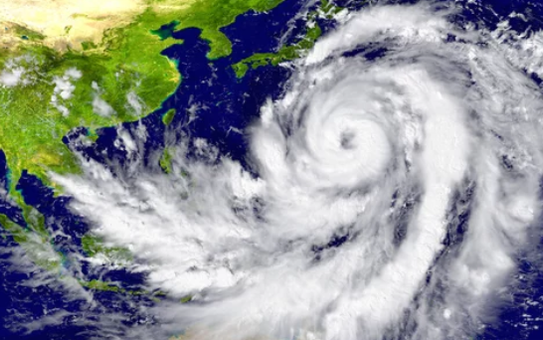
「世界一やばい台風」はどれか、具体的にご存じですか?人的被害、風速、被害額——何を基準に選ぶかで答えは変わります。この記事では、過去の災害データを指標別で詳しく分析し、日本と世界の「やばい台風」を振り返るとともに、家庭や職場での具体的な備えも解説しています。次の台風シーズンに備えて、今すぐ確認しましょう!

電気代を効率的に節約するなら「安い時間帯」を上手に活用するのがポイント!夜間の電気料金が割安になる仕組みや、地域別の料金プランを徹底解説!さらに生活パターンに応じた節電術や、家電の使い方の工夫まで詳しくご紹介します。充実した節約情報で、賢く家計を守りましょう!

災害時に本当に役立つ備えとは?停電・断水・暑さや寒さ――緊急事態で家族を守るために「なくて困るもの」をランキング形式で徹底解説!被災地の声を元に、季節や環境ごとに必要なアイテムの選び方やチェックリストを提案します。備えの常識を見直して、安心感を“進化”させましょう。