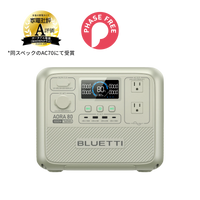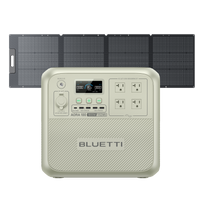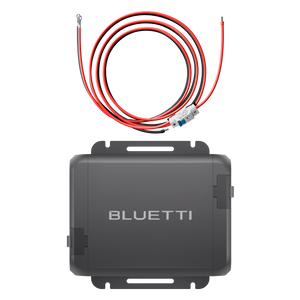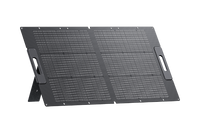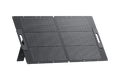車中泊を快適にするポータブル電源:具体的な選び方を紹介
車中泊を快適にするポータブル電源:具体的な選び方を紹介
車中泊用ポータブル電源の選び方
車中泊で必要なAC出力は?できれば500W以上
車中泊用のポータブル電源を選ぶ際、まず注目すべきは出力能力です。特に、AC(交流)出力のワット数が重要です。
推奨:AC出力 300W以上、できれば500W以上
車中泊で使用する機器の多くは比較的消費電力が小さいですが、電気ケトルやヘアドライヤーなどの熱を発する機器は消費電力が大きくなります。500W以上の出力があれば、ほとんどの携帯型電化製品をカバーできます。
主な機器の消費電力例
• スマートフォン充電:約10W~20W
• ノートPC:約60W~100W
• LEDランタン:約1W~10W
• 携帯扇風機:約5W~20W
• 電気ケトル:約600W~1000W(瞬間的)
• 小型電気クーラーボックス:約40W~60W

車中泊用の推奨容量:500Wh以上、できれば1000Wh以上
容量の選び方
1.使用したい機器の消費電力(W)を確認
2.何時間使用したいかを決定
3.消費電力(W)×使用時間(h)=必要な容量(Wh)
例えば、以下のような使用シナリオを考えてみましょう。
• ノートPC(60W)を3時間使用:60W × 3h = 180Wh
• LEDランタン(5W)を6時間使用:5W × 6h = 30Wh
• スマートフォン2台をフル充電(各30Wh):30Wh × 2 = 60Wh
• ポータブル冷蔵庫(50W)を8時間使用:50W × 8h = 400Wh
合計:670Wh
このシナリオでは、最低でも670Whの容量が必要となります。しかし、予期せぬ使用や将来的なニーズの拡大を考慮すると、1000Wh以上の容量があると安心です。

出力ポートの種類と数
車中泊では、複数の機器を同時に使用することが多くあります。そのため、十分な数と種類の出力ポートを持つ製品を選びましょう。
|
ACコンセント |
最低2口 |
|
USB-A |
3口以上 |
|
USB-C |
2口以上 |
|
DC出力(シガーソケット) |
1口以上 |
特にUSB-C PDポートは、最新のデバイスを高速充電できるため、あると便利です。

ブルーティパワーならではの特徴
車での高速充電機能
車中泊用ポータブル電源を選ぶ際、車での充電機能は極めて重要です。主な充電方法には、車のシガーソケットからの充電、車の屋根に設置したソーラーパネル、そして走行充電器(車のオルタネーターから)があります。特に注目すべきは走行中の充電機能です。

BLUETTI Charger 1がポータブル電源への充電時間
| モデル | 容量 | 充電スピード | フル充電時間(H) | 12V RV充電時間(H) | 24V RV充電時間(H) |
|---|---|---|---|---|---|
| AC200L | 2048Wh | 560W | 3.6 | 20.9 | 10.7 |
| AC180 | 1152Wh | 500W | 2.5 | 12.0 | 6.3 |
| AC70 | 768Wh | 500W | 2.0 | 8.2 | 4.3 |
| AC240 | 1536Wh | 560W | 2.9 | 15.9 | 8.2 |
| AC300+B300 | 3720Wh | 560W | 5.0 | 31.2 | 15.9 |
| AC300+B300K | 2764Wh | 560W | 4.7 | 27.0 | 13.0 |
| AC200MAX | 2048Wh | 560W | 3.9 | 20.9 | 10.7 |
| AC180T | 1433Wh | 500W | 3.4 | 14.8 | 7.7 |
| AC200P | 2000Wh | 560W | 5.7 | 20.5 | 10.5 |
| AC2A | 204Wh | 200W | 1.3 | 2.5 | 1.5 |
| EB3A | 268Wh | 200W | 1.4 | 3.2 | 1.8 |
| AC50B | 448Wh | 200W | 2.5 | 5.0 | 2.7 |
| AC60 | 403Wh | 200W | 2.2 | 4.5 | 2.5 |
静音性の確認
車内という密閉された空間で使用するため、ポータブル電源の動作音は重要な選択基準となります。
• ファンの騒音レベル
• 動作時の振動
• 電子音(操作時や警告音)の調整機能
特に就寝時の使用を考えると、静音性は快適な車中泊の鍵となります。可能であれば、実際に動作音を確認してから購入することをおすすめします。

持ち運びやすさと設置のしやすさ
車内での使用を前提とするため、ポータビリティと設置のしやすさは重要な選択基準となります。
考慮すべきポイント:
• サイズ:車内に収まりやすい形状
• 形状:安定して置ける平らな底面
• ハンドルの有無と使いやすさ
• 防振・滑り止め機能
また、車内での固定方法も考慮に入れましょう。急ブレーキや急カーブの際に動かないよう、固定用のベルトやフックが付属しているモデルも便利です。

拡張性と互換性
将来的なニーズの変化や、より長期的な使用を考慮し、拡張性のある製品を選びましょう。
• ソーラーパネルとの互換性(将来的なオフグリッドキャンプに備えて)
• 家庭用給電システムとの連携可能性
• ファームウェアのアップデート対応
特にソーラーパネルとの互換性は、長期の車中泊や災害時の備えとしても有用です。

付属品と専用アクセサリー
車中泊での使用を快適にする付属品やアクセサリーも、ポータブル電源選びの重要な判断材料となります。以下のような付属品が標準で含まれているかどうかをチェックしましょう。
• 車載充電用ケーブル:走行中の充電に必須
• 収納用バッグ:持ち運びや保管に便利
• LEDライト:一部のモデルに内蔵されており、夜間の利用に役立つ
これらが標準装備されていれば、追加費用を抑えられるだけでなく、互換性の心配もなくなります。特に初心者の方にとっては、使い始めの負担が軽減されるでしょう。

車中泊に関連記事

車中泊にポタ電おすすめ3選!
「車中泊に最適なポータブル電源を知りたい!」という方は多いでしょう。
この記事では、車中泊で活躍するポータブル電源の選び方や、車中泊におすすめのポータブル電源3選をご紹介します。

車の便利グッズ15選を紹介!
「車の運転や車内で過ごすときに便利なグッズを知りたい!」という方は多いと思います。
この記事では、車内に用意したい基本の便利グッズ7選と、車での旅を快適にする便利グッズ8選をご紹介します。

【厳選】車中泊の暑さ対策3選!
「夏に車中泊をしたいから、暑さ対策について知りたい」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、車中泊で暑さ対策が重要な理由、車中泊の暑さ対策3選、車中泊の暑さ対策に役立つグッズをご紹介します。
車中泊用ポータブル電源によくある質問
季節や使用する電化製品によって必要性は変わります。夏場のファンや冬場の電気毛布を使用しない場合は、スマートフォンの充電程度であればモバイルバッテリーで十分かもしれません。ただし、快適な車中泊を望むなら、あると便利です。
電気毛布は平均して50W程度の消費電力があり、8時間使用する場合は400Wh程度必要となります。そのため、500Wh以上の容量があるポータブル電源を選ぶことをおすすめします。他の電化製品も使用する場合は、さらに大容量のものを検討してください。
一般的な車中泊では、300Wh~500Whの容量があれば基本的な電化製品を使用できます。電気毛布やファンなども使用する場合は、700Wh以上の容量を検討することをお勧めしています。
特に夏場は車内放置にご注意ください。車内温度が60度以上に上昇することもあり、バッテリーの劣化や故障の原因となる可能性があります。使用時以外は室内での保管がおすすめです。必要な時だけ車に積み込むようにしましょう。