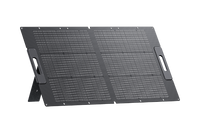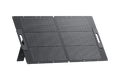「一人暮らしの電気代が高すぎる…」そんな悩みを抱えていませんか?本記事では、月々の電気代の平均額や高くなる原因、すぐに実践できる節電方法を解説。具体的な節約シミュレーションや、おすすめ節電グッズもご紹介します。
一人暮らしの電気代を見直し、無理なく節約生活を始めたい方必見です。
一人暮らしの1ヵ月あたりの電気代はどれくらい?
まずは、一人暮らしをしている方の1ヵ月分の電気代の平均をチェックしておきましょう。ただし、電気代は季節や住んでいる地域によって大きく異なるため、季節別や地域別の平均金額についてもあわせてご紹介します。
一人暮らしの月間電気代の平均は約7,155円
2024年に総務省統計局が公表している調査によると、単身世帯における1ヵ月あたりの電気料金の平均は約7,155円となっています。もし毎月の支払いがこれを大きく上回っているなら、少し電気を使いすぎている可能性もあるかもしれません。
※出典:総務省統計局「家計調査(家計収支編)2024年」
季節や地域で電気代に差が出る理由とは?
先述の7,155円という金額は、あくまでも年間を通じた平均値です。実際には、気温や気候の影響で月ごとの電気使用量が変動するため、季節ごとに支出にも差が出てきます。単身世帯の電気代を季節別にまとめると、以下のような傾向が見られます。
■単身世帯における季節別平均電気代(月額)
|
期間 |
平均月額(円) |
|
2024年1~3月期 |
7,150 |
|
2024年4~6月期 |
5,839 |
|
2024年7~9月期 |
6,771 |
|
2024年10~12月期 |
6,356 |
1年の中で最も電気代が高くなるのは、寒さが厳しい1~3月です。支払いは翌月になるため、実際の使用ピークは12月から2月と考えられます。一方、春先にあたる4~6月は、冷暖房の使用が少ないことから年間で最も電気代が抑えられる時期となっています。
続いて、地域ごとの平均電気代も確認してみましょう。
■地域別平均電気代(月額・2024年)
|
地域 |
月額電気代(円) |
|
北海道・東北地方 |
7,500 |
|
関東地方 |
6,566 |
|
北陸・東海地方 |
6,794 |
|
近畿地方 |
6,648 |
|
中国・四国地方 |
7,437 |
|
九州・沖縄地方 |
6,274 |
平均月額で最も高額だったのは北海道・東北地方でした。一方で、最も安かったのは九州・沖縄地方という結果に。特に関東や近畿といった人口の多いエリアでは、相対的に電気代が低く抑えられる傾向があるようです。
電気代の構成要素とは?

電気代は一見すると一括りに思えますが、実際には
-
基本料金
-
電力量料金
-
燃料費調整額
-
再生可能エネルギー発電促進賦課金
という4つの要素で成り立っています。それぞれがどんな役割を担っているのか、順に見ていきましょう。
基本料金
基本料金は、電気を使った量にかかわらず毎月一定額で発生する料金です。この金額は契約しているアンペア数によって異なり、アンペア数が大きくなるほど料金も高くなります。もちろん、契約アンペアを見直して下げれば基本料金を節約できますが、家庭で使う電化製品の合計使用電流がアンペア数を超えないよう調整が必要です。そのため、基本料金を大胆に削るのは現実的に難しいケースも少なくありません。
なお、関西・中国・四国・沖縄などの地域では、この基本料金方式ではなく「従量料金制(最低料金制)」が導入されています。この制度では、あらかじめ定められた最低使用量に達していなくても、最低ラインに相当する金額を毎月支払う仕組みです。
電力量料金
電力量料金は、実際に使用した電力量に応じて計算される料金項目です。算出方法はシンプルで、「電力量料金単価(円/kWh)×使用量(kWh)」となっています。
ただしこの単価は一定ではなく、多くの電力会社では使用量に応じて3段階に区分された料金設定が採用されています。たとえば、東京電力エナジーパートナーの「従量電灯B」における2024年1月時点の電力量料金は以下の通りです。
|
区分 |
単価(円/kWh) |
|
第1段階(120kWhまで) |
30円00銭 |
|
第2段階(120kWh超~300kWhまで) |
36円60銭 |
|
第3段階(300kWh超) |
40円69銭 |
※出典:東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」
このように、使えば使うほど料金が上がる仕組みのため、節電=電気代の節約につながるというわけです。
燃料費調整額
燃料費調整額は、発電に使われる燃料の価格変動を電気料金に反映させるための項目です。直近3ヵ月の貿易統計価格をもとに、燃料価格が高騰していればその分を電力量料金に上乗せ、逆に下がっていれば値引きされる仕組みになっています。
最近では原油やLNG(液化天然ガス)の価格が上昇しているため、燃料費調整額が加算されるケースが多くなっています。
また、以前はこの調整額にも上限が設けられていましたが、燃料価格の急騰を受けて上限の撤廃に踏み切る電力会社も増加しているのが現状です。なお、この燃料費調整額は利用者がコントロールできるものではないため、電気の使い方を工夫しても直接的に減らすことはできません。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、太陽光や風力などによって発電された電力を電力会社が買い取る際にかかった費用の一部を、私たち消費者が負担するために上乗せされる料金です。
この金額は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×電力使用量」で算出され、単価は国によって定められています。そのため、節約を考えるならこの賦課金自体を抑えることはできませんが、電気の使用量を減らすことで間接的に節約につなげることは可能です。
一人暮らしの電気代が高くなる理由と見直し方法

なぜ一人暮らしの電気代が思ったよりも高くなってしまうのでしょうか。考えられる原因はいくつかあり、それぞれに合った対策を取ることでコストを抑えることが可能です。
消費電力の大きな家電を非効率に使っている
エアコンや冷蔵庫、照明、テレビといった消費電力の多い家電は、使い方を誤ると電気代が無駄に膨らみやすいものです。ここでは、代表的な家電ごとの節電ポイントを押さえておきましょう。
古い家電を使い続けている
家電製品は年々省エネ性能が向上しており、古いモデルを使っているとそれだけで無駄な電力が発生するケースがあります。たとえば10年前の家電を最新の省エネ機器に買い替えた場合、エアコンで約10%、テレビで約31%、冷蔵庫ではなんと46%、照明に至っては86%の電気代削減が可能とされています。もし古い家電を使用しているなら、思い切って買い替えを検討するのも有効な選択肢でしょう。
在宅時間の長さが影響している
テレワークなどで自宅にいる時間が増えると、それだけ電力消費量も増えるため、電気代が高くなる傾向にあります。以下に、テレワークの頻度によってどの程度電気代が変わるかを示します。
■テレワーク日数別・1週間あたりの電気代(目安)
|
テレワーク日数 |
夏季(冷房) |
冬季(暖房) |
|
週2日 |
約1,230円 |
約1,388円 |
|
週3日 |
約1,845円 |
约2,083円 |
|
週5日 |
約3,075円 |
約3,472円 |
※試算条件:ノートPC(30W)、照明(10W)、エアコン(冷房580W・暖房660W)を1日8時間使用、電力量料金単価31円/kWh
このように、テレワークの頻度が高いほど比例して電気代も増加していくことが明確です。可能であれば出社と在宅勤務のバランスを調整することで、電気代を抑えることができるかもしれません。
電力会社や料金プランが生活スタイルに合っていない
契約している電力会社やプランが、自身のライフスタイルにマッチしていないことも電気代が高くなる一因です。たとえば、ファミリー向けのプランをそのまま使っていると、基本料金が割高に設定されていることがあります。
また、日中は外出が多く夜間に電気を使う生活をしているなら、夜間料金が安くなるプランへの切り替えを検討するのも良いでしょう。このように、電気をよく使う時間帯に合わせたプランに見直すことで、無理なく節約につなげられる可能性があります。
今すぐ始められる電気代節約術!消費電力の大きい家電を見直そう
2022年頃から世界情勢の変化によってエネルギーの供給が不安定となり、燃料費も大きく値上がりしました。こうした背景から、日常的に節電を意識することは家計を支える重要な手段となっています。では、どんな方法で電気代を抑えることができるのでしょうか。今日から取り入れられる節電のコツをご紹介していきます。
電力を多く消費する「冷蔵庫」「洗濯機」「テレビ」「照明器具」を見直す!

家庭で使用する家電の中でも、特に電力消費が大きいのは空調設備のエアコンや冷蔵庫、洗濯機、照明、テレビといった機器です。それぞれの家電における効果的な節電ポイントを見ていきましょう。
冷蔵庫
冷蔵庫は、家電の中でもトップクラスに電力を使う機器のひとつです。冬場は冷却力を「弱」に設定し、消費電力を抑えるのが得策です。また、庫内に物を詰め込みすぎると冷気の循環が悪くなるため、適度な隙間を保つよう意識しましょう。さらに、冷蔵庫の背面や側面から熱を逃がす構造になっているため、壁から少し離して設置するのも節電効果があります。
照明器具
蛍光灯からLEDへの切り替えは、消費電力の削減に非常に効果的です。LEDは蛍光灯の半分ほどの電力で同じ明るさを確保でき、寿命も長いため結果的にコストパフォーマンスに優れています。特に長時間使用するリビングルームなどには、早めの導入を検討してみる価値があります。
テレビ
液晶テレビは、バックライトの明るさを調整するだけで消費電力を抑えることができます。設定を少し暗くするだけでも、電力の消費をぐっと抑えられる場合があります。明るさの自動調整機能がついているテレビなら、周囲の明るさに応じて最適な明るさを保ってくれるため、節電にもつながります。
エアコン
冬の寒さ対策でエアコンを使用する際は、設定温度の上げすぎに注意が必要です。例えば、室温が10度の部屋で設定温度を25度にすると、大量の電力を使って温度を上げようとします。効率よく暖めるには風向きを下向きに設定するとよいでしょう。さらに、部屋全体を暖めるのではなく、着込んで自分の体を保温する工夫もおすすめです。
炊飯器
炊飯後の「保温」を長時間使い続けると、それだけで炊飯と同等の電力を消費することがあります。3~10時間の保温で電力が無駄になるため、炊き上がったら早めに電源を切り、食べる分だけ温め直すのが節電のコツです。
給湯器
意外と見落とされがちなのが、ガス給湯器のリモコンパネルです。実は待機電力が多く、家庭全体の待機電力の約2割を占めるともいわれています。お湯を使わないときは、こまめに電源をオフにしておきましょう。
電気・ガスをまとめて節約!セット割プランの活用も有効

日常の節電努力も重要ですが、それに加えて契約している電力会社やプランの見直しを行うことも、節約には欠かせません。中でも注目したいのが「電気とガスのセット契約」です。こうしたプランを提供している会社では、両方をまとめることで料金が割引される場合があります。
また、金銭的なメリットだけでなく、生活の安心をサポートする付加サービスが付く場合も。たとえば、東京電力エナジーパートナーが提供する「生活かけつけサービス」では、停電、水漏れ、窓ガラスの破損、鍵のトラブルなどに24時間365日対応。必要な部品代も最大2万円まで無料となっており、作業費や出張費もかかりません。こうしたサービスは、一人暮らしの方にとっても心強い存在となるはずです。
ポータブル電源を導入して電力コストを賢く節約!
ポータブル電源を取り入れることで、毎日の電気代を効率的に抑えることが可能になります。たとえば、電気料金が安くなる夜間に充電しておき、日中の高い時間帯にその電力を使用すれば、トータルのコストを下げられるというわけです。
さらに、ソーラーパネル対応モデルを選べば、昼間の太陽光を使って自家発電することもできます。電力を自給自足できるので、節電だけでなく防災アイテムとしても重宝します。
なかでも注目したいのが、BLUETTI(ブルーティ)のポータブル電源シリーズ。性能や容量のバリエーションが豊富で、安全性にも定評があり、多くのユーザーに支持されています。
ここでは、電気代の節約に特に役立つおすすめモデルをピックアップしてご紹介していきます。
BLUETTI AORA 100 大容量ポータブル電源でかしこく節約&非常時にも安心!
BLUETTIの「AORA 100」は、1152Whの大容量と1800Wの高出力を兼ね備えた高性能なポータブル電源。家庭での普段使いから、いざという時の備えまで、幅広く活躍してくれる一台です。
-
冷蔵庫を7.4時間、テレビを14時間も動かせるため日中の電力需要に対応。停電時の備えとしても非常に心強い存在です。
-
夜間の安い電気料金で充電し、日中にその電力を使用すれば、ピーク時の電力消費を抑えて節約効果を発揮。
-
ふだん使いしながら非常時にも役立つという“フェーズフリー”の考え方にもぴったりのアイテムです。
加えて、「AORA 100」には最先端の急速充電機能が搭載されており、45分で80%まで充電が可能。夜間の電気料金の安い時間帯に充電するにもぴったりです。
さらに、ソーラーパネルからの充電にも対応しているため、日中の太陽光を使って自家発電も可能に。電気代の節約はもちろん、災害時の電源確保としても心強い存在です。1台あるだけで、日常も非常時も安心を提供してくれます。
実際どれだけ節約できる?東京電力「夜トクプラン」でシミュレーション
たとえば、東京電力の「夜トク8」プランを活用し、「AORA 100」を夜間にフル充電したうえで日中に電力を使用した場合、どれほどの節約が見込めるのか、試算してみましょう。
|
内容 |
数値 |
|
ポータブル電源容量 |
1,152 kWh |
|
昼夜電力単価差 |
10.96 円/kWh |
|
1日あたりの節約額 |
約12.63 円 |
|
1か月あたりの節約額 |
約379 円 |
|
1年あたりの節約額 |
約4,548円 |
このように、夜間に充電して日中に電力を使うだけで、年間4,000円以上の節約が可能です。
1,152 kWhと聞くと「そんなに電力使うかな?」と疑問に思うかもしれません。そこで、日常生活の中での現実的な使用例をご紹介します。
|
使用家電 |
使用時間・回数 |
消費電力量 |
|
ノートパソコン |
8時間 |
400Wh |
|
LED照明(夜間) |
6時間 |
240Wh |
|
スマホ2台充電 |
各2回 |
40Wh |
|
炊飯器 |
1回 |
約300Wh |
|
電子レンジ |
15分 |
150Wh |
|
合計 |
— |
1,130Wh |
このように、日常的に使う家電やデバイスの電力をカバーするだけで、容量をしっかり活用できることがわかります。無理なくフル活用できる設計だからこそ、節電にも防災対策にもおすすめできるのです。
一人暮らしを始める人へ!電力会社と料金プランの選び方ガイド

電気代を抑えるには、まず自分に合った電力会社と料金プランを選ぶことが大切です。ここでは、電力自由化の活用方法や、電力会社選びのコツ、切り替え手順までをわかりやすく解説します。
電力自由化で広がる節約のチャンス
かつては、電気を家庭向けに販売していたのは東京電力や関西電力など、地域ごとに決まった電力会社のみでした。消費者が選べる選択肢はなく、電気は“地域の会社から買うもの”というのが当たり前でした。
しかし、2016年4月に電力の小売全面自由化がスタートしたことで、状況は一変。今では誰でも自由に電力会社や料金プランを選べるようになりました。
新規参入の「新電力」を選ぶこともできますし、居住地とは異なるエリアの電力会社と契約することも可能です。さらに、再生可能エネルギーを中心とした供給を行う事業者から電気を買う選択肢も生まれました。
最近では、電気とガスや、電気とスマホなどをセットにした割引サービスも増えており、こうした組み合わせを上手に活用すれば家計の負担をさらに軽減できます。
電力会社を選ぶときのチェックポイント
電力会社を選ぶ際には、まず自分の生活スタイルに合った料金プランを見つけることが第一歩です。日中家にいる時間が長いのか、それとも夜間の使用が多いのかなど、自分の電気の使い方をふまえて選ぶようにしましょう。
加えて、契約期間の縛りや解約時の違約金の有無、ポイント還元制度の有無も確認しておきたいところです。各社が独自に展開しているキャンペーンや特典も見逃せません。これらを総合的に比較することで、よりお得な契約先を選ぶことができるはずです。
電力会社を変更するには?手続きの流れ
電力会社を切り替える方法はとても簡単です。希望する会社のホームページや電話、または店頭窓口から申し込むことができます。今契約している会社の解約手続きについては、基本的に新しい電力会社が代行してくれるため、自分で手続きをする必要はありません。
電力の自由化によって会社同士の競争が活発になり、利用者にとっては料金面でもサービス面でもメリットが増えました。ぜひ、自分の暮らしにぴったりの電力会社とプランを選んで、無理なく節約を実現してみてください。
なお、切り替え時に必要な情報や準備書類、手続きにかかる日数などは、各電力会社の公式サイトなどで確認しておくと安心です。
毎日の生活に取り入れたい!おすすめ節電グッズ4選
日々の暮らしの中で、手軽に始められて効果も期待できる節電グッズをご紹介します。無理なく続けられるアイテムばかりなので、ぜひチェックしてみてください。
LED照明なら年間5,296円の節約に!
照明を蛍光灯からLEDに替えるだけで、ぐっと電気代を抑えることができます。LEDの魅力は何といってもその長寿命。1日あたり10時間使用したと仮定すると、以下のような差が出ます。
-
蛍光灯:約13,000時間(およそ3年7ヶ月)
-
LED電球:約40,000〜60,000時間(約11年)
さらに、LEDは少ない電力でもしっかり明るく照らせるため、同じ12畳向けの天井照明を比較した場合、年間で約5,296円の差が生まれる計算です。
|
種類 |
1時間あたりの電気代 |
年間電気代 |
|
蛍光灯シーリングライト |
約3.1円 |
約9,078円 |
|
LEDシーリングライト |
约1.2円 |
约3,782円 |
冷蔵庫カーテンで夏の冷却効率UP!年間1,598円の節電

冷蔵庫の冷気が外に逃げるのを防ぎ、冷却効率を高めてくれるのが「冷蔵庫カーテン」です。特に、外気との温度差が大きくなる夏に活躍します。
環境省の調査によれば、冷蔵庫の設定温度を「強」から「中」に下げるだけで、年間で約61.97kWh=約1,598円の電気代削減が可能。冷気の流出を防ぐこのアイテムは、見た目以上に優れた節電効果を持っています。
節電タップで待機電力をカット!年間907円の節約も
家電の「待機電力」は意外と侮れません。節電タップを使えば、コンセントを抜かなくてもスイッチ一つで待機電力をカットできます。夜間や外出時など使っていないタイミングでオフにしておくだけで、無駄な消費を抑えられるのが魅力です。
家庭内の消費電力の約7.3%が待機電力とも言われており、以下の機器を節電タップで管理すれば、年間約907円分の節電が実現します。
|
家電機器 |
待機電力(W) |
|
HDD/DVDレコーダー |
3.4W |
|
エアコン |
2.6W |
|
デスクトップPC |
2.0W |
|
空気清浄機 |
1.7W |
|
テレビゲーム機 |
1.4W |
|
加湿器 |
0.9W |
なお、スイッチ部分のランプが消費する電力は商品によりますが、年間で20円程度とわずかです。
ワットチェッカーで節電意識を「見える化」
コンセントと電源コードの間に差し込んで使用する「ワットチェッカー」は、実際に使った電力量をリアルタイムで金額表示してくれるアイテムです。
直接的に節電効果があるわけではありませんが、「この家電ってこんなに電気を使っていたんだ!」と気づくことで、節電への意識が高まりやすくなるのが大きなメリットです。
まとめ:BLUETTIのポータブル電源で節約の一歩を踏み出そう!
一人暮らしの電気代は、使い方や工夫次第で大きく節約できます。生活スタイルに合ったプランの選択や、節電グッズの活用、ポータブル電源の導入はその第一歩。日々のちょっとした意識と対策が、将来的な節約にもつながります。
まずはできることから始めて、無理なくスマートな節電生活を始めてみませんか?
この記事から商品を購入する
関連記事

白物家電とは?暮らしを支える家事家電の選び方と、停電に強い整え方
冷蔵庫・洗濯機・エアコン…毎日の生活を支える白物家電、どれを選べば後悔しない?定義から消費電力の目安、家族構成に合った容量選び、省エネ・静音・デザインの最新トレンド、停電時の優先順位まで徹底解説。買い替えや新生活準備に役立つ実践的なポイントが満載です!

年末の大掃除を楽に進める計画術と便利アイテム完全ガイド
年末の大掃除、負担に感じていませんか?起源から事前準備、場所別(キッチン・浴室・リビング)の掃除ポイント、時間目安、効率アップの3大テクニックまでを徹底解説。ナチュラル洗剤の使い分けや断捨離コツも満載で、今年こそスムーズにピカピカの家で新年を迎えましょう!

60Hzと50Hzの違いで家電が使えない?引っ越し・停電で慌てないための周波数ガイド
東日本50Hz、西日本60Hz——同じ100Vでも周波数が違うと、電子レンジが動かない、扇風機が弱くなる…そんなトラブルが起きやすい!引っ越し前に知っておきたい家電の見分け方、地域早見表、影響の大きい家電リスト、ヘルツフリーの選び方を徹底解説。事前チェックで無駄な買い替えを防ごう!