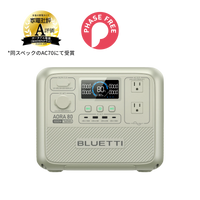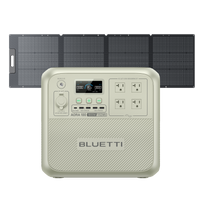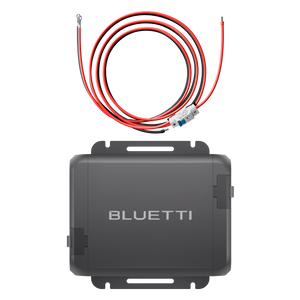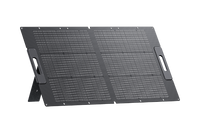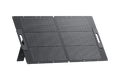発生の切迫性が指摘されている南海トラフ地震。震度7や津波による深刻な被害が広域に及ぶと予想されており、心配される方も少なくないでしょう。生存するためには、完璧な準備が不可欠です。本記事では、南海トラフ地震の基礎知識から想定される被害地域まで詳細に説明いたします。記事の終わりにはチェックリストも掲載しております。個人でできる日頃の準備についても、直ちに点検してみてください。
南海トラフ地震とは?要点をおさらいしよう。

テレビやニュースでよく耳にする南海トラフ地震。馴染みのない用語になんとなく自分ごとではないと感じている方も多いのではないでしょうか。まずは知っておくべきポイントを抑えましょう。
南海トラフはどこにある?
「南海トラフ」とは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側、土佐湾、そして日向灘沖までの海底地形を表します。ここは、フィリピン海プレートとユーラシアプレートがぶつかり合うプレート境界に存在する海溝型の地形です。トラフとは、深さが6,000メートル未満の幅広い海底の谷を指します。
この海域で起こる南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘にかけたプレートの境界が震源域となる巨大地震で、約100年から150年ごとに発生してきました。
なぜ南海トラフで地震が発生するのか?
南海トラフに沿ったプレート境界では、フィリピン海プレートが年数センチの速度でユーラシアプレートの下へと潜り込んでいます。この動きにより、ユーラシアプレートには長期間かけてひずみが溜まっていきます。
やがてそのひずみが臨界点に達すると、ユーラシアプレートが反発するように大きく動き、地震が起こるのです。この一連のメカニズムは周期的に繰り返されており、南海トラフ地震が定期的に発生するとされる理由にもなっています。
約100〜150年ごとに繰り返される大地震
過去の記録を確認すると、南海トラフでは100〜150年の周期で巨大地震が発生しており、1946年にはマグニチュード8.0の昭和南海地震が起きています。それから約80年が過ぎ、プレート間のひずみは確実に蓄積されています。そのため、将来的な発生リスクは毎年高まり続けているのが実情です。
南海トラフ地震の予想される発生時期と地震の前兆
大きな被害が想定される南海トラフ地震はいつ起こる可能性があるのでしょうか。最新の予測と防災に役立つ地震の前兆をご紹介します。
地震発生のリスクが高まっている現在の状況
南海トラフ地震は、約100年から150年の周期で継続的に発生しており、前回の昭和南海地震(1946年)から既に80年近くが過ぎています。政府の地震調査委員会は、今後30年以内にマグニチュード8〜9規模の地震が発生する確率を70〜80%と評価しています。正確な発生日の特定は不可能ですが、プレートのひずみの蓄積や過去の周期を考慮して、準備しておくことが重要です。
地震の前に見られるかもしれない前兆について
南海トラフ地震の発生前には、以下のような異常現象が観測される場合があります。
- 地鳴りや異音の発生
- 小規模な地震(群発地震)の回数増加
- 地面のゆっくりとした動き(スロースリップ)
- 海底の隆起や沈降
これらの兆候がすべて地震に直結するわけではありませんが、予兆として注意を向け、緊急事態に備えておくことは大切です。非常食や飲料水の準備、避難経路の確認など、日常的に準備を進めておきましょう。
南海トラフ地震で想定される被害と地域とは

政府は、南海トラフで巨大地震が起きた場合の被害想定を発表しています。2025年4月時点で、防災対策が求められるのは1都2府26県707市町村に達し、茨城県から沖縄県までの広域が対象となっています【※参考資料1】。これらの地域には、以下のいずれかのリスクが存在します:
- 震度6弱以上の強い揺れが想定されている
- 津波高が3メートル以上と見込まれ、海岸堤防が脆弱
- 過去の南海トラフ地震で大きな被害を受けた履歴がある
- 周辺自治体と連携した防災体制を構築する必要がある
特に震度7の揺れは、静岡県から宮崎県にかけての10県149市町村で想定されており、深刻な被害が心配されています。
※参考資料1:内閣府「南海トラフ地震防災対策 地震防災対策推進地域」
専門家が考える被害のシナリオ
「全割れ」と「半割れ」が引き起こす異なる被害想定
南海トラフ地震では、震源域全体が一度に動く「全割れ」と、東西で時間差をもって動く「半割れ」の2つのパターンが予測されています。
「全割れ」は、太平洋側全域を同時に襲うケースで、震源域全体が一気にずれることで甚大な被害が生じるシナリオです。一方で、専門家が警戒する「半割れ」は、東側と西側が時間差で揺れるケースです。
「半割れ」のシナリオでは、2度目の揺れに都市が耐えられない心配が生まれています。現在の建築基準では、連続する大地震への耐性は十分とは言えません。さらに深刻なのが「救助活動の遅れ」です。1回目の地震の直後、再び大規模地震が起こるリスクがあるため、被災地への支援が大幅に遅れる可能性があります。この複合的な影響が、「半割れ」の恐ろしさを際立たせています。
想定想定される死者数・津波の高さ・震度
「全割れ」が起きた場合、最悪で32万3,000人が死亡、約238万6,000棟の建物が全壊すると計算されています。津波の浸水被害やライフラインの断絶も深刻で、影響は広域に及びます。「半割れ」が東側で起きた場合の想定では、死者は約7万人、建物の損壊も深刻とされます。西側が割れた場合の想定では、死者は約10万人、津波による被害も大きいと予測されています。
南海トラフ地震が起きた場合の津波は、広域に到達することが見込まれます。特に太平洋沿岸では高知県や静岡県などで最大30mを超える津波が予測されており、地震だけでなく津波への対策も重要です。
更に南海トラフ地震の厄介な点は、震度7レベルの巨大地震が連発する可能性があるということです。国が想定したマグニチュード8.9の「西半割れ」地震のシナリオでは、西日本の四国・近畿・九州では震度7の激しい揺れが想定される一方、関東や静岡周辺では震度3〜4と比較的軽度な揺れになる見込みです。しかし一方の揺れがもう一方の引き金となる可能性があり、「東半割れ」が発生すると、愛知・静岡・三重では震度7、さらに関東甲信・近畿地方にも震度6強〜6弱の揺れが広がると予想されています。
津波やライフラインの被害想定は?
津波の危険性が高い地域
南海トラフ地震が起きた場合、津波の被害が特に心配されているのは静岡・高知・三重の3県です。これらの地域は津波の到達が早く、地形的にも浸水しやすい特徴があります。
例えば1946年の昭和南海地震では、高知・和歌山を中心に10m超の津波が襲来し、多数の死者と甚大な家屋被害を出しました。
現在の予測では、以下のような津波が想定されています:
|
津波の高さ |
影響範囲 |
|
3m超の津波 |
福島~沖縄にかけた25都府県 |
|
10m超の津波 |
関東~九州にかけた13都県 |
|
局地的には30m超 |
静岡や高知で発生の可能性 |
またより精密な地形データに基づいた解析により、30cm以上の浸水面積は従来より30%増加し、約11万5,000ヘクタールに及ぶとされています。
最大約3,690万人が断水も。インフラ機能の停止と生活への影響
地震と津波の影響で、最大約3,690万人が断水する恐れがあり、東海地方では95%復旧に約8週間を要すると見込まれています。
さらに送電設備が被害を受ければ、最大2,950万軒が停電し、特に電柱倒壊など物理的な損傷は復旧に1〜2週間かかる可能性があります。
ガス供給にも支障が出るとされ、最大175万戸で供給停止となり、完全復旧まで最長5週間が必要とされています。
このようなライフライン被害により、地震発生から1週間後には最大約1,230万人が避難生活を強いられると予測されます。近畿圏では帰宅困難者が約280万人に達する見通しです。
物資不足も深刻で、初動3日間で最大約1,990万食の食料と約4,370万Lの飲料水が不足することが心配されています。
過去の南海トラフ地震から見る危険地域と安全地域

南海トラフ沿岸地域においては、昔から一定の周期で大規模な地震が起こり続けています。およそ100〜150年のスパンでマグニチュード8級の巨大地震が反復して発生しており、こうした歴史的データは、今後の地震発生予測や災害対策立案における極めて重要な基礎資料として位置づけられているのです。南海トラフにおける過去の実例を検証してみると、その発生メカニズムには相当な変動性が見て取れます。広範囲が一斉に地震を引き起こしたケースもあれば、マグニチュード8級の大地震が近隣区域において時間的なずれを伴って起こる場合もあるのです。こうした発生パターンの変動性こそが、南海トラフ地震の予想と対応策を困難にする主要因となっており、多種多様なケースを想定した事前準備が求められています。
過去の地震で特に被害が甚大だった県は?
1854年の安政南海地震では、高知県を中心に津波が襲い、四国沿岸や紀伊半島で大きな被害が起きました。1946年の昭和南海地震でも、房総半島から九州まで津波が到達し、特に高知県で甚大な浸水被害が発生しています。
1944年の昭和東南海地震では、静岡・愛知・三重などで約2万6,000棟が全壊、998人が死亡しました。1946年の昭和南海地震では、高知などで約1万1,500棟が全壊し、死者は1,330人にのぼりました。1854年の安政東海地震でも、東海沿岸や内陸部で大きな建物被害が記録されています。
南海トラフ地震が起きても、比較的安全とされる地域とは?
過去の記録からは、長野、岐阜、群馬、栃木、山梨、滋賀などの内陸県では被害が限定的だったことが判明しています。また、北海道や東北地方(青森、岩手、秋田など)も比較的影響を受けにくい地域とされています。
ただし、南海トラフ地震は広範囲にわたる影響があるため、どこにいても備えは不可欠です。被害が少なかった地域でも、油断せずに防災対策を心がけましょう。
南海トラフ地震で安全とされる地域ランキング
南海トラフ地震では全国的に甚大な被害が見込まれますが、比較的安全な地域も存在します。この章では安全な地域について説明します。
被害リスクが少ない地域の条件とは?
標高が高い地域
南海トラフ地震の被害を最小限に抑えられる地域には共通点があります。内陸や高地は被害を受けにくく「生き残れる可能性」が高いとされます。また、地盤が強固で液状化のリスクが低い地域も、安全性が高い環境といえるでしょう。
内陸部や津波リスクが低い地域
内陸部に位置する県は、南海トラフ地震による被害が少なく、生存する確率が高いと考えられています。震源から遠く津波の心配がない内陸県は、過去にも被害が少ない傾向が見られます。ただしいつ何が起こるかわからないので、万が一の備えはどの地域であっても必須です。
比較的安全とされる地域・都道府県ランキング
南海トラフ地震で起こりうる被害を考慮した際、比較的安全とされるエリアを以下の3つの項目別にランキングでまとめました。(データに基づいた客観的な安全性評価を参考に、適切にご活用ください。)
|
順位 |
地震の揺れが比較的少ない県 |
地盤が安定している県 |
津波の被害を受けにくい県 |
|
1位 |
北海道 |
沖縄県 |
長野県 |
|
2位 |
秋田県 |
群馬県 |
岐阜県 |
|
3位 |
山形県 |
福島県 |
群馬県 |
|
4位 |
青森県 |
栃木県 |
栃木県 |
|
5位 |
岩手県 |
熊本県 |
山梨県 |
これらの県は、他の県に比べて安全性が高いと言われています。
ただし、備える必要がないという訳ではありません。油断せずに家具の固定や備蓄などの対策は徹底して行いましょう。
南海トラフ地震で危険とされる地域の特徴

ここでは地震そのものだけでなく、津波や液状化、避難困難などの要因に注目し、南海トラフ地震でとくに危険とされる地域の特徴を見ていきます。
被害リスクが高い地域ランキング
特に津波リスクが高いエリア
沿岸部の低地は南海トラフ地震で津波による被害が深刻化しやすいと言われています。特に静岡県、高知県、三重県は津波の到達が早く、地形的に浸水範囲が広がりやすい傾向にあります。実際過去に起きた昭和南海地震では、高知県で10メートルを超える津波が観測されたという記録が残っています。日頃から津波に備えて避難経路や高台の位置を確認しておくことはどの地域でも重要ですが、特にこの地域に住んでいる人は準備をしておくと良いでしょう。
地盤や人口集中が起因の被害予想エリア
地盤の性質や人口分布も、被害の規模を決定する重要な要素となっています。高知県、新潟県、岡山県では、軟弱地盤による液状化現象や斜面崩壊のリスクが指摘されています。これらの地域は河川の堆積作用で形成された平野部が多く、地震の揺れが増幅されやすい地質構造を持っています。速やかな避難準備と、安全な避難先の確認が欠かせません。
そして大阪府、愛知県、静岡県のような人口集中地域では、避難時の混乱が最大の脅威となります。交通網の麻痺、避難施設の収容能力不足、建物倒壊による避難路の閉塞など、都市部特有の問題が複合的に発生する恐れがあります。阪神・淡路大震災でも、人口密度の高い地域で火災が発生し、避難の妨げとなりました。
危険地域の居住者が取るべき最優先の行動とは?
南海トラフ地震のリスクが高い地域に住む方は、万が一の時に備えて「行動の優先順位」を明確にしておくことが必要です。特に「津波からの避難」は一刻を争います。
揺れを感じたら、まずは身の安全を確保してください。倒れやすい家具や落下物から身を守るため、机の下などに避難しましょう。地震の揺れが止んだ瞬間から、すぐに安全な高台へ向かうことが生存の鍵となります。
津波避難においては、事前の準備が成否を左右します。避難経路と目的地を複数パターン用意し、家族全員が把握しておくことが重要です。津波は何度も押し寄せる性質があるため、警報解除まで避難を継続する必要があります。海岸線や河川沿いにいる場合は、とにかく内陸の高い場所を目指しましょう。
南海トラフ地震から安全に生き残るための対策

南海トラフ地震では、揺れそのものに加えて津波、家具転倒など複数の危険が同時に発生します。比較的安全とされる内陸部でも、物流の停止により生活物資が不足する事態が予想されます。生存確率を最大化するための準備について説明します。
(1) 避難行動の計画を立てておく
事前に避難経路を確認
緊急時に冷静で的確な判断を下すためには、平常時からの入念な計画が不可欠です。津波浸水の可能性がある地域では、自治体が作成したハザードマップを活用して、お住まいの場所における津波リスクを正確に把握してください。防災対策強化地域に指定されている場所では、特に注意深い準備が求められます。わずか30センチの津波でも人命に関わる危険があることを忘れてはいけません。複数の避難ルートと避難場所を設定し、家族間で情報を共有することが重要です。離れた場所にいる親族との連絡方法についても、あらかじめ相談しておきましょう。
避難時の注意点
津波は地震発生から数分という短時間で沿岸部に到達するため、素早い対応が生死を分けます。激しい揺れを体感したら、躊躇することなく標高の高い場所へ移動してください。海岸や河川の近くでは、津波避難ビルや避難タワーを積極的に利用しましょう。最寄りの避難場所が遠い状況では、3階建て以上の堅牢な建物への緊急避難も有効です。津波警報が発表された際は、絶対に海岸線には近づかず、正確な情報収集を継続してください。
(2) 家庭内でも備えを万全にしておく
家具の固定、耐震補強
住宅内での安全対策は、地震による直接的な被害を最小限に抑える最も基本的な防御手段です。地震による死傷者を防ぐには、家具類の転倒対策と住宅の耐震性向上が絶対条件となります。阪神・淡路大震災の犠牲者の多くは、家具の下敷きになったことが原因だったという調査結果があります。家具の配置変更や固定器具の設置によって、この種の事故は大幅に減らすことができます。寝室や玄関付近に不安定な家具がある場合は、別の場所への移動を検討してください。
家族間での連絡手段と集合場所の調整
先ほど避難計画でも述べましたが、家族の安否を確認するシステムと集合地点の事前決定は欠かすことができません。東日本大震災の際は、通常の通信手段が機能せず、家族間の連絡が取れない状況が長期間続きました。災害用伝言ダイヤル171、災害用伝言板Web171、各種SNSの災害時利用方法を学んでおくことをお勧めします。避難所の場所や経路について家族で話し合い、全員が同じ認識を持っておくことも大切です。
(3) 防災備蓄をしっかり用意しよう
備蓄リスト
災害後の生活を維持し、救援体制が整うまでの期間を乗り切るための備蓄は極めて重要です。被災地から離れた場所でも、流通網の寸断により物資が不足する可能性があります。したがって、高リスク地域に限らず、相対的に安全とされる地域の住民も、十分な備蓄が必要です。各家庭で以下の防災用品を必ず用意してください。
|
分類 |
備蓄品目 |
必要量・期間 |
|
食料・水分 |
保存食品、飲料水 |
最低1週間分を確保 |
|
生活用品 |
簡易便器、調理用具、情報機器など |
家族構成に応じた適量 |
|
電源設備 |
充電式電源装置、予備電池 |
長期停電に対応できる容量 |
この備蓄リストについては、この後でより詳細に解説し、記事の最後にはチェックリストも用意しています。
南海トラフ地震に備えて準備したい実用アイテム
ここでは南海トラフ地震への備えとして、実際に役立つ実用的なアイテムをご紹介いたします。
太陽光発電対応のポータブル電源製品
電力供給の途絶に対する準備は、災害時の生活維持において極めて重要な要素となります。電力が遮断された状況では、照明の確保が精神的な安定と直接的に結びつきます。周囲が真っ暗になると、転倒や怪我のリスクが高まるだけでなく、心理的な圧迫感も増大してしまいます。災害発生後の電力復旧には1〜2週間程度を要するケースが多く、充電式の照明器具だけでは途中で電池切れを起こす危険があります。そこで威力を発揮するのが、ソーラーパネル搭載型ライトや太陽光発電機能付きの電源装置です。昼間の日差しを利用して継続的に蓄電できるため、長期間の停電状況でも安定した電力を確保できます。
日本限定モデルBLUETTI AORA 100 V2 ポータブル電源

BLUETTIが日本市場向けに特別開発したAORA 100 V2は、日本語での表示機能により、誰でも直感的に操作できる仕様となっています。十分な充電を済ませておけば、緊急時でも安定した電力供給を維持できます。
前世代モデルと比較して30%以上の軽量化を実現しているため、避難時の携行も容易で、一般家庭の防災対策に最適な設計となっています。操作方法も分かりやすく、一台備えておくだけで大きな安心感を得られます。もちろん太陽光による充電機能も搭載されており、天候に恵まれた日であれば70分という短時間でフル充電を完了できます。
BLUETTI Apex 300 大容量ポータブル電源

高容量タイプのポータブル電源であるBLUETTI Apex 300は、アウトドア活動はもちろんのこと、災害時の備えとしても家族全員の生活をしっかりとサポートします。「電力リフト機能」により最大6,400Wという大出力に対応し、一般的な家庭用電化製品であれば問題なく稼働させることができます。ほとんどすべての電気機器に幅広く対応できる設計で、停電が長期化した場合でも継続的な電力供給を実現します。充電方式も多様な選択肢が用意されており、当然ながら太陽光発電による蓄電も可能となっています。
防災セット

南海トラフ地震においては、多種多様な被害の発生が見込まれています。道路や鉄道といった交通インフラの破綻により、物資の流通が長期間にわたって停止する可能性も十分に考えられるため、生活に不可欠な防災用品の事前備蓄が極めて重要となります。照明器具、清潔用品、簡易式トイレ、医療用品、保温具などについても、自宅保管用と緊急持ち出し用の両方に分けて、漏れのないよう準備しておきましょう。
情報収集に必要なアイテム
緊急事態においては、普段利用している通信手段が機能しなくなるケースが頻繁に発生します。平常時とは異なる情報入手ルートを複数確保しておくことが極めて重要となります。携帯可能なラジオ受信機は、電波の受信環境さえ整っていれば確実に利用できるため、非常事態での情報収集において非常に有効な手段です。普段使用しているものとは別に、スマートフォン用の予備充電装置も防災用バッグに常備しておくと、いざという時の備えとして心強い存在となります。
南海トラフ地震に強い地域で住まいを探すには?
南海トラフ地震は日本各地に甚大な影響をもたらすと想定されています。そんな中、危険度の低い地域への居住地変更を検討される方々もいらっしゃるでしょう。
安全地域の条件とは?
南海トラフ地震の影響を抑制可能な地域には共通点が存在します。海抜が高い山間部や地質が堅固な場所が危険度を下げるとされているのです。津波到達の可能性が低い高地や、震動が軽微になりやすい場所も該当します。人口集中が進んでいない点も考慮すべき要素でしょう。転居先選定時は、地勢や土壌の条件についても調査されることをお勧めします。
津波被害を想定して、新しい引越しエリアを検討する
地震が引き起こす津波は生命を脅かす深刻な脅威となります。このため予防策の準備が不可欠です。東日本大震災における犠牲者の多くが津波により命を失ったという事実があります。津波から身を守るための新天地への転居を考える方もいることでしょう。津波の脅威から距離を置ける地域には、長野・岐阜・群馬・栃木・山梨各県が含まれます。これらは内陸性の立地により、津波危険度が抑えられているためです。
防災対策に力を入れている自治体はどこ?
防災施策に熱心な行政機関は、過去の震災経験を活用した取り組みを実施しています。たとえば過去に大きな損害を受け、将来的にも相当な被害が懸念される静岡県においては、防災インフラの強化が推進されています。避難経路の充実化や住民向け防災学習を推進する地域も存在することから、国が発表する「防災対策推進地域一覧」において現住所や移住候補地が該当するかどうか、事前に調べることを推奨します。
南海トラフ地震の際に安全な地域に関するよくある質問
安全とされる地域であれば備えは不要?
被害想定が軽微な地域においても、準備は決して欠かしてはなりません。危険度が低いとされる場所でも、地震による家屋破損や電力供給停止が起こり得ます。生活必需品の確保や緊急時対応の準備は、居住地域に関係なく重要となります。
安全な地域であれば事前調査は不要?
住居の地震対応力を調べずに入居することは、極めて危険な行為と言えるでしょう。1981年より前に建てられた構造物は従来基準での施工のため、崩壊の危険性が増大します。構造診断を実施し、問題があれば補強工事や再建築を検討すべきです。地方自治体の中には支援制度を整備している場合もありますから、それらを効果的に利用して安全な居住環境を整えてください。
安全とされる地域に住んでいない場合はどうしたら良いの?
リスクの高い場所にお住まいの方は、避難体制の整備と緊急物資の確保が何より大切となります。周辺の避難施設と移動ルートを把握し、防災用品の充実も図りましょう。特に南海トラフ地震においては、広域災害による長期間の避難生活が想定されます。避難の長期化を見据えて、ポータブル電源などの準備も行っておくことをお勧めします。
まとめ:南海トラフ地震は「いつ起きても不思議じゃない」
南海トラフ地震は今後10年間で約8割の発生確率とされており、いつ発生してもおかしくない状況となっています。その規模は東日本大震災の10倍に相当する損害が予想されるため、生命保護のための行動を直ちに開始する必要があるでしょう。
被害を減らすには「備え」と「計画」がすべて
損害を最小化するためには、地域危険度の理解と物資確保の徹底が欠かせません。危険予測図の検証、家具転倒防止措置や建物補強工事、脱出ルートの把握など、現在実施可能な対策に家族全員で着手しましょう。生存のためには、「準備」と「避難戦略」こそが全てなのです。
日常に“備える習慣”を取り入れよう
わが国は地震発生国・世界第4位に位置するほど、震災の起こりやすい環境にあります。地震への慣れは、緊急時における適切な判断力を鈍らせてしまう恐れがあります。南海トラフ地震の影響は東日本大震災を上回る程度になると考えられており、日頃からの準備体制が危機的状況での生命線となるでしょう。定期的な対策見直しを行い、備蓄習慣を身につけてください。
ポータブル電源は長期避難生活の“安心材料”
震災後は長期間の電力不足やライフライン破綻が見込まれます。準備する防災用品リストにポータブル電源を加え、少しでも快適に過ごせる環境づくりを進めましょう。BLUETTI製品のような太陽光対応で長時間稼働する電源装置があれば、避難時の不安感も和らげられます。
防災意識を持って“選択する暮らし”を
「常に脱出可能な状態」「どんな事態でも生き抜ける体制」そうした安全を確保するため、現在の準備が将来へと結びついていきます。防災に有効なアイテムリストも準備しておりますので、ぜひご活用ください。