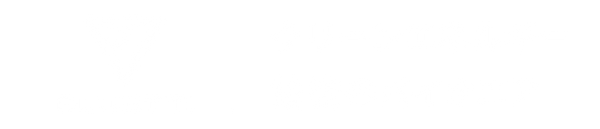手ぶらで渡ればハラハラのサバイバル、用意万端で臨めば五感がほどけるリトリート。同じ島でもまったく違う顔をのぞかせてくれる自由度こそ、無人島旅の醍醐味だ。
無人島サバイバルとは?まず準備すべきこと4選
上陸後に直面するのは「水・食・寝床・火」の4課題である。以下ではレジャー型とセルフ型の違いを踏まえ、初日に取るべき手順を整理した。
無人島サバイバルの2タイプ|レジャー型とセルフ型の違い
レジャー型はガイド艇や非常通信が用意され、万一の水・食料も補給できる。よって荷物は軽量化がカギになる。はじめて無人島を体験するなら、難易度や装備が比較的やさしい“レジャー型”を選びましょう。一方、セルフサバイバル型は「助けが来ない」を前提に装備を二重化し、天候悪化でも3日しのげる備蓄が必須だ。
◆基本4ステップ
① 水の確保
日帰りなら1.5L/人+浄水ストロー(差し込んで直接飲めるストロー型フィルター)。泊まり以上は携帯フィルター+0.5Lの塩抜きタブレットを重ね、安全域を広げる。
② 食の手当て
非常食パック200kcal×人数×日数を底に敷き、釣り具や貝ナイフで現地調達分を上乗せする。
③ 寝床づくり
テント+タープが基本。軽量化したい場合はハンモック+バグネット(全周メッシュ蚊帳)で代用し、高潮線より2m上の高所を選ぶ。
④ 火と灯りは用意が安心
固形燃料は風に強いが湿気で点きにくい。フェロセリウムロッド(雨でも火花が飛ぶ金属棒/着火用)と防水マッチの三本立てにすると嵐でも火が失われない。
上陸した途端、日常の便利はすべて砂の向こうへ置き去りにされる――この感覚こそ無人島の醍醐味だが、同時に油断できない境界線でもある。
無人島に持っていくべきものリスト【用途別まとめ】
荷物は「目的別に束ねる」と忘れ物チェックと荷重管理が一度で済む。本章では5カテゴリに分けて紹介する。
◆ 水と火
ペットボトル水: 一人1.5Lを最低限準備。滞在が長くなる場合や高温の日はさらに多く持参。
携帯浄水フィルター: 自然の水源(川や湧水)を浄化し、泥や細菌を取り除くフィルター。飲み水を確保できる安心アイテム。初心者にはストロー型フィルターがおすすめです。
塩抜きタブレット: 海水を半量程度の飲用水に変えるための道具。長期滞在時や水の補充が難しいときに役立つ。

フェロセリウムロッド: 雨の日でも火が起こせる頑丈な金属棒。火花を発生させ火口材に着火可能。マッチやライターが湿気で使えないときの保険に最適。
防水マッチ: 濡れても火が点く特殊加工マッチ。持っていて損はありません。
固形燃料: 風に強くすぐ火が点く燃料剤。嵐や湿気の多い日でも役立つ。1人3~5個ほどで十分。
◆ 食と調理

非常食パック: 開封してすぐ食べられるアルファ米など。カロリー消費が激しいため1人200kcal×滞在日数分用意がおすすめ。軽量で長期保存可能なものが便利。
チタンポット & 折り畳み五徳: 軽量かつコンパクトな調理器具。煮沸消毒、調理、湯沸かしなど多用途に使える。
基本調味料3種: 塩は電解質補給、オイルは高カロリー源、七味は消臭効果があり、料理の風味も向上させる。ガラス瓶ではなく、小分け可能なプラスチックボトルで準備
◆ 衛生と安全
ディート30%虫よけ: 蚊やブヨ、マダニを避けて刺されるのを防ぎます。(※ディート濃度の高い虫よけは特に効果的)
固形石けん: 海水でも泡が落ちやすいサバイバル用石けん。少量で十分です。
ゴミ袋(45L×2枚): ゴミの持ち帰りは基本ルール!臭いや液漏れも防ぎ、無人島をきれいに保つ意識を忘れずに。
応急キット: 止血シートは小さな傷の感染を防ぎ、経口補水粉末は脱水症状時に水へ溶かして電解質を補給、痛み止めは頭痛や筋肉痛などを和らげます。軽量なポーチにまとめ、事前に使い方を確認しておくと安心です。
◆ 寝床とウェア
ドームテント+軽量タープ: 雨風防御を二重化し、快適なスリーピングエリアを確保。初心者は地域の気候も考慮して耐水性の高いものを選びましょう。
ラッシュガード(UVカット)+ 薄手ダウン: 昼は暑さ、夜は冷え込み対策に重要なアウター。速乾性素材なら濡れても保温性を保てる。
防水スニーカー: 足元の滑り防止。軽量で岩場やぬかるみを歩きやすい靴が◎
◆ アクティビティ+電源
パックロッド 80cm(振り出し式コンパクト竿)+小型リール: コンパクトに収納できる「パックロッド」と「小型リール」は、小さなバックパックにも収まるため、持ち運びが便利です。魚釣りに挑戦することで、現地調達の楽しさを体験することができます。
BLUETTI AORA 30 V2(ポータブル電源): スマートフォンやヘッドライトなど、無人島での基本的な電化製品を充電するのに最適なコンパクトなポータブル電源です。緊急時にスマホを数回充電できる288Whの容量なら、短期の滞在には十分対応可能です。

BLUETTI AORA 100 V2(大容量バッテリー): 1,024Whという大容量は、LEDランタンだけでなく、60Wの冷蔵庫を約13時間稼働させられるため、冷たい飲み物や生鮮食品をストックしておきたい場合に安心です。ドローンを使用する場合も約25分で充電完了、自然風景をライブ感覚で楽しめます。
こうして“グループ化”しておくと忘れ物チェックが一目で済み、荷重の見積もりも立てやすい。
★初心者はまずコレだけ:
水 2L+携帯フィルター/防水マッチ/非常食 3 食/虫よけスプレー/1 人用テント/AORA30V2。(合計重量は約 5kg で、公共交通でも運びやすい。)
無人島キャンプで失敗しやすい持ち物例

取材と体験談から“荷物のしくじり”を集約。共通点を押さえれば、余計な重量と水ストレスを減らせる。
◆ よくある失敗と教訓
・ビーチサンダルだけ→岩場で負傷 ▶滑りにくいアクアシューズ必須(手頃な代替は“踵ストラップ付きマリンシューズ”)
・香り付きシャンプー→海水で泡切れず環境負荷 ▶固形せっけん少量で充分
・着替えを日数分フル装備→濡れて重い ▶速乾ウエア2セット+洗濯ロープで回す
・調味料をフルボトル→ガラス重量 ▶100mlボトルに小分け
POINT: 「真水で流せない」「乾かせない」状況を想像し、軽さ・多用途・水不要を合言葉に削ぎ落とすと失敗が減る。
無人島での注意点と心得|安全&エコのために
トラブルの九割は“知っていれば避けられる”ものばかり。許可・気象・環境の3ブロックに凝縮してチェックリスト化した。
① 許可と規制
・島ごとに所有者と消防の許可を取得。余島は神戸YMCAへ3日前までに申請。
・広島県条例で「直火禁止」区域あり――焚き火台+耐熱シートを持参。
② 水・天候・体調
・「膝下、流速0.5m/s超えたら渡渉中止」が鉄則
・潮汐表はスクリーンショット保存、バッテリー節約
・熱中症サイン(めまい・倦怠感)を仲間と共有し“声掛けライン”を決める
③ 動植物とゴミ
・サンゴ・海藻エリアに石けん使用NG
・ゴミは45L袋二重+アルミ蒸着で防臭、持ち帰り前提
・外来種混入を防ぐため、帰宅後は靴底を漂白水で洗浄
サバイバル体験ができる日本の無人島3選

所在地・特色・アクセス・火規制を横並びにしたので、旅程の比較表としてご活用いただきたい。
◆ 余島(兵庫県・瀬戸内海)
・ベストシーズン: 4–10 月(クラゲが少なく水温も安定)
・特色: 干潟観察+シュノーケルを同日に体験/ファミリー向け
・アクセス: 赤穂港から渡船 15 分/要 YMCA 予約
・ガイド: 有り(救援ボート常駐で安心)
・火規制: 焚き火台+耐熱シート必須、直火禁止
・島 Tip: 干潮の 1 時間前に潮だまりへ行くとヤドカリ観察◎
◆ ありが島(山口県・周防大島沖)
・ベストシーズン: 5–11 月(台風シーズンを除く)
・特色: 釣り+採集で“完全自給”に挑戦/上級者・ソロ向け
・アクセス: 大島大橋から車 40 分→渡船 5 分
・ガイド: 無し(完全セルフ/緊急連絡は衛星電話推奨)
・火規制: 風速 5m/s 超は焚き火自粛要請
・島 Tip: 北岸はフナムシ多、南岸の岩礁はカサゴが濃い
◆ 龍王島(広島県・安芸灘)
・ベストシーズン: 7–9 月(ウミホタル発光ピーク)
・特色: ウミホタル×星景写真が撮れる“映え”スポット/カップル・カメラ好き向け
・アクセス: 安芸津港から定期船 25 分/要 管理組合許可
・ガイド: 事前講習のみ(撮影講座あり)
・火規制: 雨天は固形燃料+フェロロッド併用が無難
・島 Tip: 満潮直後に浜へ出ると発光量が最大になる
サバイバルに強い!無人島でも使えるポータブル電源

平日はベランダのBBQでホットプレートを稼働させ、週末はキャンプ場でLEDランタンを灯し、台風による停電時には冷蔵庫の温度を維持する──こうした「日常と非常時を一台でまたぐ」ライフスタイルを〈フェーズフリー〉と呼ぶ。BLUETTIのAORAシリーズは、その概念を体現するポータブル電源である。
AORA 30 V2は片手でつかめるコンパクトボディながら、LEDランタンを約15 時間点灯させ、スマートフォンを10台フル充電できる288 Whの容量を備える。USB-C出力は100 Wに対応し、ドローンバッテリーをおよそ25分で満充電にできる。重量は約3.4 kgで、2リットルのペットボトルと水筒を合わせた程度しかないため、バックパックのサイドポケットに無理なく収まる。
対してAORA 100 V2は1,024 Whの大容量を誇り、60 Wの家庭用冷蔵庫を約13 時間、100 Wのモバイルプロジェクターを4 時間連続で稼働させても余裕がある。採用するリン酸鉄リチウム電池は充放電3,000回超の耐久性を持ち、長期使用でも劣化が目立ちにくい点が安心材料だ。晴天時には180 Wのソーラーパネルでおよそ7 時間で満充電が可能なため、無人島でも「昼間に発電し、夜に楽しむ」というサイクルを無理なく構築できる。
※島によっては「全面直火禁止」。固形燃料だけでなく、フェロロッドや防水マッチを併用し、焚き火台の下に耐熱シートを敷くこと。湿度80%超の日は木が着きにくいため、固形燃料は予備を含め1人あたり3タブレットあると安心だ。
よくある質問
Q: 無人島キャンプで初心者でも挑戦できる?
A: はい、初心者向けの「レジャー型無人島サバイバル」ならガイド付きで安全に体験可能です。
Q: 飲み水はどれくらい持って行くべき?
A: 日帰りなら1人あたり最低1.5L。滞在が長くなる場合は、携帯浄水フィルターや塩抜きタブレットを併用し、現地で安全に水を補充しましょう。
Q: 無人島で火を起こす最も簡単な方法は?
A: フェロセリウムロッドを使う方法が簡単で確実。雨の日や湿気の多い環境でも火花を飛ばして着火できます。マッチや固形燃料と併用するのが無難です。
Q: 夜はどれくらい寒くなる?何を用意すべき?
A: 夜間は地域や季節によりますが、20℃以下になることが多いです。薄手ダウンジャケットやタープで防寒対策を必ず取りましょう。
まとめ
無人島旅行は、自然と調和しながら冒険心を満たす特別な体験です。安全対策をしっかり整え、お気に入りのアイテムを持っていけば、まるで教室のように新しい学びと発見に溢れた時間になるでしょう。
フェーズフリーなポータブル電源があれば、その余白にほんのり明かりと涼風を添え、冷えた飲み物で喉を潤しながら星を数えることもできる。夕陽で海が黄金に染まる頃、塩と汗が肌に残ったままコットに大の字になり、空を流れる雲に次の航海のルートを描いてみてほしい。無人島は不自由の象徴ではなく、自由を思い出す教室だ。安全第一で、けれど少しだけ大胆に——次の物語を開きに行こう。