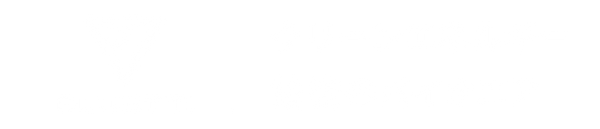関東には、手軽にアクセスできる低山から、本格的な稜線歩きを楽しめる標高の高い山まで、多彩な登山スポットが点在しています。忙しい日常から少し離れ、自然の香りを胸いっぱいに吸い込むと気分がリフレッシュしますよね。今回は、私が実際に登ってみて感じたことや、周囲の登山仲間から聞いた生きた情報を交えながら、関東地方の登山事情をご紹介します。初めての方も、装備やルート選びに迷わないよう具体的なヒントを詰め込みました。ぜひ、山の魅力を再発見してみてください。
関東のおすすめ登山スポットいろいろ
I. アクセス抜群の低山で、まずは肩慣らし
高尾山
-
標高: 599メートル
-
シーズン: 春~秋(通年可、夏冬は装備が必要)
-
所要時間: 約1~3時間
-
難易度: 初心者向け
都内から電車で行ける東京・八王子市の山です。ケーブルカーやリフトがあり、登山に慣れていない人でも気軽に山頂を目指せます。晴れた日には富士山が見えることも。混雑を避けたいなら、朝早めのスタートがおすすめです。
御岳山
-
標高: 929メートル
-
シーズン: 春~秋
-
所要時間: 約2~4時間
-
難易度: 初心者~やや中級向け
青梅市にあり、ケーブルカーで標高800メートルほどまで一気に上がれる山です。山頂近くには「武蔵御嶽神社」が鎮座しており、古くから山岳信仰を集めてきました。神社をお参りしてから、苔むしたロックガーデンを巡るコースも静かな雰囲気が魅力で、観光客が多い高尾山とはまた違う落ち着きがあります。夏場でも比較的涼しく、アクセスも良いため、のんびりハイキングを楽しみたい初心者や家族連れに最適です。
II. 関東平野を一望できる二つの名山
筑波山
-
標高: 877メートル
-
シーズン: 春、秋(通年可だが夏冬は要注意)
-
所要時間: 約2~4時間
-
難易度: 初心者~中級向け
男体山・女体山の双耳峰を縦走できる山で、関東平野の大パノラマを一望できます。ロープウェイやケーブルカーを活用すると、登りと下りを変えられて飽きません。春と秋がベストシーズンといわれています。
鋸山(乾坤山)
-
標高: 約329メートル
-
シーズン: 通年(夏は熱中症に注意)
-
所要時間: 約2~3時間
-
難易度: 初心者~やや中級向け
かつて大規模な採石場として栄えた歴史をもつ山で、削り取られた岩肌が独特の風景を生んでいます。ロープウェイを利用すれば短時間で山頂近くまで行けるうえ、麓からのルートでは適度な運動量を確保しながら、海沿いならではの潮の香りも楽しめます。同じ低山でも内陸にある筑波山とは違い、海の広がる風景がポイント。「地獄のぞき」と呼ばれる断崖はスリル満点で、海鮮が味わえるお店やフェリー乗り場も近いので、観光と組み合わせて日帰りで満喫できます。
III. 自然豊かな奥多摩・秩父エリア
宝登山
-
標高: 497メートル
-
シーズン: 通年(冬~春は花の見頃)
-
所要時間: 約1~3時間
-
難易度: 初心者~中級向け
ロープウェイで山頂近くまで行けるので、家族連れでも挑戦しやすい山です。冬のロウバイや春の梅・桜など、四季の花々も楽しめます。
大菩薩嶺
-
標高: 2057メートル
-
シーズン: 4月~11月
-
所要時間: 約3~5時間
-
難易度: 中級向け
標高2000メートル超の山で、高山の雰囲気を味わいたい人にぴったり。稜線に出ると富士山や南アルプスの迫力ある景色を望めます。車で中腹まで行けるため、日帰りプランも組みやすいです。
IV. 群馬・栃木の山々で本格派を目指す
谷川岳
-
標高: 1977メートル
-
シーズン: 6月~10月
-
所要時間: 約4~6時間
-
難易度: 中級向け
岩壁のイメージがある山ですが、天神尾根コースなら比較的穏やかな稜線歩きを楽しめます。天気が変わりやすいので、防寒具とレインウェアは必須です。
那須岳
-
標高: 1916メートル
-
シーズン: 5月~10月
-
所要時間: 縦走で4~6時間(コースによる)
-
難易度: 中級向け
火山の迫力が魅力の山域で、ロープウェイを使って一気に標高を稼ぐことが可能。三本槍岳や茶臼岳を組み合わせた縦走が人気です。
日光白根山
-
標高: 2578メートル
-
シーズン: 5月~10月(残雪期は上級)
-
所要時間: 往復約5~6時間
-
難易度: 中級~上級向け
丸沼高原からロープウェイを利用し、標高2500メートル台へ。標高が高いため気温が低く、天候が変わりやすいので注意が必要です。
V. 高山を諦めない、でも安全第一
三ツ峠
-
標高: 1785メートル
-
シーズン: 4月~11月
-
所要時間: 約3~5時間
-
難易度: 中級向け
富士山近辺に位置し、春~秋が登りやすいです。往復で3~5時間ほどかかるので、無理のない計画を立てましょう。
丹沢の大山
-
標高: 1252メートル
-
シーズン: 通年(春・秋が快適)
-
所要時間: 約2~4時間
-
難易度: 初心者~中級向け
標高はそこまで高くありませんが、朝晩の気温がぐっと下がる日もあるので防寒具は忘れずに。日帰りで行きやすいので、時間のない週末にもおすすめです。
いずれの山も標高1500メートル前後から急に冷え込むことが多いので、夏でもフリースやウインドブレーカーを用意しておくと安心です。私もかつて軽装で寒さに震えたことがあり、それ以来いつも厚手の上着を持ち歩くようにしています。天気が怪しいときは早めの撤退を心がけ、「山頂まで行かなくても楽しめる」という余裕を持つのが大切ですね。
どんな山に登るにしても、以下の装備や計画が大切です。次は、初心者でも安心して登れるための必需品をご紹介します。
登山に必要な道具って?
I. 靴選びがすべての土台
登山靴は自分の足に合っているかどうかが、本当に大切です。実際、靴のサイズが微妙に合わずに靴擦れを起こしてしまい、帰りの下り道が地獄のように感じたことがあります。標高が低い山ならトレッキングシューズでもいいですが、標高が高い場所に行くなら、ソールが硬めでしっかり足首をサポートしてくれるタイプがおすすめです。お店で試し履きをするときは、靴下もいつも登山に使う厚手のものを持参して、かかとが浮かないか、つま先に余裕があるかをきちんとチェックしてみてください。
II. ザックの容量を考える
日帰りの山歩きなら、二〇リットルから三〇リットルくらいのザックでだいたい事足ります。もし山小屋やテント泊を予定しているなら、四〇リットル以上の容量があったほうが安心です。ザックは背負ってみないと意外とフィット感がわからないので、お店で荷物を入れて背負い比べるのがベスト。背中が蒸れにくいかどうかや、肩ベルト・腰ベルトが自分の体型に合っているかも、しっかり確認してくださいね。
III. レイヤリングで温度調節
山の天気はとにかく変わりやすいです。歩き始めは体が温まって暑く感じても、休憩すると汗が冷えて「寒い…」と思うことも。そんなときに大事なのがレイヤリング。ベースレイヤー、ミドルレイヤー、アウターの3段構成を基本にして、こまめに脱ぎ着して温度を調節します。汗をかいてもすぐに乾いてくれる素材のウエアを選ぶと、体力の消耗を防げるので便利ですよ。
携帯や電子機器の充電って大切?
長時間の山行では、スマートフォンでの地図アプリやGPS機能が頼りになります。ですが、写真撮影やSNS投稿を続けていると意外とバッテリー消費が早いですよね。山小屋があっても自由に充電できるとは限りませんし、非常時に連絡が取れなくなるのは大変危険です。
そこで頼りになるのが、大容量のポータブル電源。たとえば Bluetti Elite 200 v2は、2,073.6Wh の大容量と 2,200W の高出力を備えており、複数の機器を同時に充電できるのが心強いですね。AI-BMS(バッテリー管理システム)を搭載しているため、バッテリー残量や出力を自動制御してくれます。夜間でも安心して充電作業を任せられるのが魅力です。
もっと軽量な選択肢がいいなら、 ポータブルパワーバンクも便利です。こちらは 153.6Wh の容量があり、ノートPCやタブレットの充電に対応できます。USB-Cポートが 100W の双方向充電に対応しているので、登山仲間とのシェアや同時充電にも重宝するでしょう。
安全対策と登山計画のコツ
I. 天気情報は逐一チェック
山の気候は本当に変わりやすくて、晴れのはずが急に雷雨に見舞われたり、稜線で強い風に吹かれたりすることがあります。私も「今日は大丈夫だろう」と甘く見て出かけて、ずぶ濡れで帰ってきた経験があるんです。だからこそ、出発前には天気予報や山の公式サイトを忘れずにチェックしてください。標高が高い山ほど気温も下がるので、防寒着や雨具はいつでも使えるように準備しておくのがおすすめです。
II. 余裕を持ったコースタイム設定
ガイドブックに載っているコースタイムは休憩をほとんど考慮していないことが多いので、初めて行く山なら1.5倍くらい多めに見積もって計画を立てると安心です。登り始めからペースを上げすぎると、下山の頃には足がガクガクになってしまうこともあります。私もかつて「余裕で行けるだろう」とタカをくくって痛い目を見たことがありました。無理をしないように、こまめな休憩を挟むのがおすすめですよ。
III. 食料と水分補給
たとえ日帰りでも、水分と行動食はしっかり持参したいところです。スポーツドリンク、チョコ、ナッツ、エネルギーバーなどは手軽にエネルギーや塩分を補えるので重宝します。特に夏場は思った以上に汗をかきますし、秋や冬でも汗をかいたあとに風で冷えることもあるので、こまめに少しずつ飲食して体調を整えてください。
IV. 非常時のために
山の中で道に迷ったり、体調が急に悪化したりした場合を考えて、緊急連絡先や近くの山小屋・避難小屋の情報をメモしておくと安心です。スマホのGPSは確かに便利ですが、バッテリー切れや電波が入らないエリアに入るリスクもあります。紙の地図やコンパスをサブとして持っていれば、いざというときに落ち着いて行動できるはずです。
登山旅行を成功させるヒント
 I. テーマを決める
I. テーマを決める
「山頂から富士山を眺めたい」「秋の紅葉のトンネルをくぐりたい」など、自分なりのテーマを設定すると、モチベーションが上がります。行き先の山を調べながら、その山ならではの見どころをリストにすると楽しみが膨らみます。
II. 小さな達成感を積み重ねる
低山からスタートし、だんだん高度を上げていくと、無理なく体力がつきます。最初から急登や長時間のコースに挑むと、「登山ってしんどい…」と思ってしまうかもしれません。山登りは継続が大事。少しずつステップアップしましょう。
III. こまめにログを残す
初めての山に行ったときの天候やコース、服装、所要時間などをメモやアプリに残しておくと、次回以降の計画に役立ちます。自分の体力や歩行ペースもおおよそ把握でき、山選びが楽になりますよ。
よくある質問(FAQ)
関東で登るべき山は?
アクセスを重視するなら高尾山がおなじみですね。もっと遠くの雄大な景色を味わいたいなら、筑波山や大菩薩嶺なども人気があります。初心者の方は、ケーブルカーやロープウェイが整備されている山を選ぶと、無理せず楽しめると思いますよ。
日本一難しい登山ルートはどこですか?
よく名前が挙がるのは、北アルプスの剱岳(つるぎだけ)や、冬季の谷川岳にある岩壁ルートなどでしょう。かなり高度な技術と経験が必要なので、登山を始めたばかりの方には正直おすすめできませんね。
登山でやってはいけないことは何ですか?
自分の体力や装備以上に無理をしてしまうこと、ゴミを捨てること、決められた登山道を外れて自然を荒らしてしまうことなどは厳禁です。みんなが気持ちよく楽しむためにも、最低限のマナーは守りたいですね。
ハイキングとトレッキングと山登りの違いは何ですか?
明確な線引きは人によってちょっと違うんですが、標高差や歩行時間で区分することが多いです。標高差があまりなく、観光に近い雰囲気ならハイキング、装備を整えて長い距離を歩くならトレッキング、そして明確に登頂を目指すスタイルなら山登りと呼ぶケースが多いですね。
まとめ
関東地方には、手軽に行ける低山から二千メートル級の本格的な山まで、本当にいろいろな選択肢があります。気軽に気分転換したいときは高尾山や御岳山がちょうどいいですし、もう少し難易度を上げたいなら大菩薩嶺や谷川岳も候補に挙がります。さらに登山をしっかり満喫したい方には八ヶ岳周辺など、多彩なルートがそろっているんですよ。調べ出すと「こっちも行きたい、あっちも気になる」と、候補がどんどん増えて困るくらいです。
初めて山に挑戦するときは、安全面の配慮と装備選びがいちばん大切だと思います。しっかりした靴や雨具があれば、天候が変わっても落ち着いて動けますし、スマホやカメラをたくさん使うならポータブル電源があると安心ですよ。こうした便利グッズが充実しているおかげで、初心者でも自然を思いきり楽しめるようになりました。
最後に、山に入ると自然の雄大さやパワーを全身で感じられる反面、自分の体力や準備不足を痛感する場面もあるかもしれません。でも、それも含めて登山のおもしろさ。焦らず少しずつ経験を重ねながら、安全第一で目の前に広がる絶景を楽しんでほしいですね。