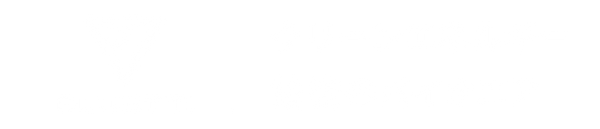――突然の停電で真っ暗になったわが家。止まった給水ポンプに焦り、バッテリー残量5 %を切ったスマホを握り締めて「しまった!」と声が出た――。
「備えていたはずなのに、いざという瞬間に“肝心なものが足りない”と悟る」。これは、私が熊本取材で耳にした被災者Nさん(30代)の実感そのものでした。地震・台風・豪雨など多様な災害にさらされる日本では、何を揃え、どう保管し、家族でどう共有しておくかが生活再建までのスピードを大きく左右します。本稿では、被災地のヒアリングで挙がった「なくて困ったもの」を徹底的に掘り下げ、場所・年齢・季節ごとに“本当に役立つ備え”を組み立てます。
なぜ「備えていたのに結局困る」のか──本当に足りなかったモノは?

日本列島は南北に約3,000 km——つまり北海道の流氷と沖縄のサンゴ礁が同居するほど、気候の“振れ幅”が大きい国です。真夏に40℃近くまで気温が上がる内陸盆地があれば、真冬に氷点下20℃を下回る豪雪地もある――。この地理的バリエーションがそのまま災害の“顔ぶれ”を複雑化させています。
-
1995年の阪神・淡路大震災では、都市直下型ゆえのインフラ損壊が深刻で、水道復旧まで最長90日・停電は最長11日と長期化。
-
2011年の東日本大震災では津波と原発事故が重なり、「避難が長期化し、仮設住宅で冬を越す」という新たな課題が浮上。
-
2019年の令和元年東日本台風(台風19号)は関東甲信を縦断し、広域浸水で1,000か所超の道路が寸断、物流網が数日間ストップしました。
-
2020年の令和2年7月豪雨は熊本を中心に発生。避難所が密になりがちなコロナ禍と重なり、さらに真夏日が続いたことで冷房不足から熱中症搬送が相次ぐ二重苦となりました。
同じ「停電」でも、冬なら暖房・給湯が止まり低体温リスク、真夏なら冷房停止で熱中症リスク。水害なら飲料水が汚染される懸念、地震なら断水でトイレが機能不全――と、困るポイントが季節と災害種別で劇的に入れ替わります。
だからこそ「とりあえず非常食と懐中電灯」という一枚岩の備えでは不足が露呈しやすいのです。地域・季節・家族構成で“困りごと”の中身を具体化し、備蓄と防災ギアをカスタマイズする――これが、想定外を最小化する唯一の道だと言えるでしょう。
被災者アンケートで判明!本当に困ったモノTOP 5

以下は熊本地震、19号台風、令和2年豪雨――被災経験者312名に聞いた「切実度ランキング」を私なりに再編したものです。
| 順位 | なくて困ったもの | 困った理由・エピソード |
| 1 | 飲料水・食料 | 想定より早く在庫が尽き、給水車には午前4時から寒空で順番待ち——「赤ちゃんのミルクが足りない」と涙ぐむ母親もいた。 |
| 2 | トイレ関連(簡易トイレ・凝固剤) | 避難所のトイレは行列。自宅避難でも排水が止まり使用不能になった。 |
| 3 | 電力(照明・スマホ充電) | 停電3日目。モバイルバッテリーが枯れ、LINE既読も付かない"情報ブラックアウト"に突入した。 |
| 4 | 暑さ寒さ対策 | 真夏の車中避難で40℃近い車内温度、真冬の体育館床で低体温症寸前になったケース。 |
| 5 | 情報ツール(ラジオ・充電池) | スマホもラジオも沈黙し、役場の広報車が来るまで「何が起きているのか分からない」時間が続いた。 |
上表のように「水・トイレ・電気」の三要素が不動の上位。特に電力は"複数日"という時間軸で見ると被災直後より深刻度が増します。
避難場所別に備えるべきアイテムと注意点

避難場所によって「足りなくなる物」は驚くほど変わります。下記4パターンを例に、想定外の欠品をつくらないコツをまとめました。
自宅避難
断水と停電が同時に来ると、まず飲料水とトイレ処理剤が底を突きます。
3階建てなら階ごとに2 ℓペットボトルを分散し、トイレ凝固剤は家族人数×3日分が最低ライン。
灯りは乾電池式ランタンが安全です。夜間の転倒を防ぐため、階段や廊下に足元灯を貼り付けておくと安心。
公共避難所(学校・公民館など)
もっともストレスになるのがプライバシーと睡眠環境。仕切り用のレジャーシート、耳栓、アイマスクをセットで持参しましょう。パーテーション代わりに段ボールを立てるだけでも、周囲との距離感が心理的負担を大きく下げてくれます。
車中避難
エンジンを回し続ければ燃料がみるみる減ります。車載シガーからだけでなく、外部のポータブル電源に切り替えて扇風機やスマホを充電するのが現実的。
排気ガスを逃がすため、窓を数センチ開けて"即席網戸"(防虫ネット+ガムテ)を貼ると一石二鳥。夜風が入るだけで体感温度は想像以上に下がります。
屋外の高台・公園
雨風と紫外線を一度に遮る多機能ポンチョが重宝します。
水場が遠い場合は、携帯浄水器や折りたたみポリタンクで飲料水の確保を。
真夏は熱中症、真冬は低体温症へ一直線の環境なので、体温調節できるレイヤリング(薄手のダウン+レインウェア)を"着る備蓄"として意識してください。
年齢・性別別に見る「ないと困るもの」チェックリスト

被災現場のヒアリングを重ねると、「家族で備えていたはずなのに、いざという瞬間に役立たなかった」という声が少なくありません。その要因の大半は、年齢や性別ごとの"こまやかなニーズ"を見落としていたことにあります。乳幼児・女性・高齢者が安心して避難生活を送るためには、次のような"パーソナル備蓄"の視点が欠かせません。
赤ちゃん・子ども
哺乳瓶の洗浄が難しい避難所では液体ミルクが便利。一方で粉ミルクも1週間分は自宅に置いておくと安心です。
お気に入りの絵本やぬいぐるみは"匂いと触感"で心を落ち着けるセーフティブランケットの役割を果たします。
女性
生理用品は「自分に合うサイズ・素材」を3周期分。配給品は種類が限られがちで肌トラブルの原因になるため、普段使いのブランドをそのまま備蓄するのが鉄則です。
替えショーツと速乾インナーはジップ袋で圧縮し、防水と省スペースを両立させましょう。
高齢者
常用薬は7〜14日分を個包装し、お薬手帳のコピーを同封。
仮設トイレ用のポータブル手すりや滑り止めスリッパは転倒事故を大幅に減らします。
段差や暗い廊下を想定して、LED足元灯を一緒に用意しておくと夜間の移動が安全です。
メンタルヘルス・快適グッズ
長期避難では"暇つぶし"が心の薬になります。トランプやUNO、塗り絵、オフラインで遊べるタブレットゲームをバッグに1つ。笑い声が生まれるだけで周囲の緊張が和らぎます。
季節別・備えて安心チェックリスト

夏は熱中症と虫刺され、冬は低体温と結露カビ。「停電=ただ暗くなるだけ」ではない、という事実がここにあります。以下に代表的アイテムと"何に効くか"をまとめました。
夏の災害
充電式扇風機と冷感タオルで体の熱を逃がし、氷のうを首や脇に当てれば深部体温も下げられます。
蚊取り線香やDEET成分入りスプレーは感染症媒介の蚊を遠ざける必需品です。
冬の災害
アルミ保温シートは体温の放射を約80 %反射し、寝袋の内側に入れるだけで3 ℃前後の温度アップ。使い捨てカイロや湯たんぽは"局所加温"で血流を維持し、凍傷を防ぎます。
カセットガスストーブは必ず一酸化炭素警報機とセットで使用し、換気のタイミングをアラームで管理しましょう。
定番必需品15選 —— "回る備蓄"でローリングストック
| カテゴリ | アイテム | 目安量(3日分/1人) |
| 水分 | 飲料水 2Lペットボトル | 9L |
| 水分 | 経口補水液パウダー | 3袋 |
| エネルギー | 主食系非常食(アルファ米・パン缶) | 9食 |
| エネルギー | 加熱剤付きレトルトご飯 | 3食 |
| 嗜好 | 甘味・塩味スナック | 適量 |
| 嗜好 | インスタント味噌汁/スープ | 6袋 |
| 情報 | 手回しラジオ+乾電池 | 単3×8本 |
| 通信 | モバイルバッテリー(10,000mAh以上) | 1台 |
| 電力 | ポータブル電源(Apex 300 推奨) | 1台 |
| 衛生 | 簡易トイレ+凝固剤 | 10回分 |
| 衛生 | ウェットシート/アルコールジェル | 1パック |
| 照明 | LEDランタン | 2基 |
| 照明 | ヘッドライト | 1個 |
| 多目的 | 布ガムテープ/結束バンド | 各1巻 |
| 保温 | アルミ保温シート | 1枚 |
ポータブル電源が買えない場合、小型のモバイルバッテリーやソーラー充電器を活用すると低コストで電力を確保できます。
意外と使えなかった防災グッズとは?
防災用品を購入する際には、硬すぎる非常食や大きくて重いプラスチック容器など、不要なものは避ける必要があります。
・固すぎる非常食バー…歯が弱い高齢者は食べられず。→おかゆパウチに入れ替え。
・大型ポリタンク…満タンでは持ち上がらない。→2 L×6本箱へ分散。
・手動発電ライト…数分で腕が疲れて断念。→USB充電式+ソーラー併用モデルへ。
「有名だから」「テレビで見たから」ではなく、"自分が実際に使えるか"を基準に取捨選択を。反省点こそ次回の改善点です!
家族を守る、進化した防災ギア3選

――停電しても「冷蔵庫が止まりません」「スマホが切れません」「夜が真っ暗になりません」。
ポータブル電源は、家庭用コンセントをそのまま持ち運べるバックアップ電源です。バッテリー・インバーター・複数の出力端子が一体化しており、自宅避難でも車中泊でも電気に関するストレスを丸ごと肩代わりしてくれます。ここでは、その代表格を三台だけ厳選しました。
BLUETTIのポータブル電源は、「フェーズフリー」のコンセプトに合致し、災害時だけでなく平常時にも活用できます。災害時に身近なものを活用し、非常時でも安心感を維持することが、フェーズフリーのコンセプトの本質です。
BLUETTI Apex 300(2764.8 Wh/3200 W)
冷蔵庫、IH炊飯器、洗濯機を同時に稼働できます。停電が48時間続いても生活リズムを崩さない頼れる心臓部です。
BLUETTI AORA 100 V2(1024 Wh/1800 W)
車載移動や避難所の共有スペースに最適です。ホットプレートで温かい食事を作りながら、スマホを八台同時に急速充電できます。
BLUETTI AORA 30 V2(288 Wh/600 W)
重さはわずか4.3キログラム。避難経路でも片手で運べる"ハンドキャリー電源"です。LEDランタンを九時間点灯でき、スマホなら約二十回フル充電できます。
平常時はアウトドアや花火大会の電源として、非常時はライフラインとして活躍します。まさにフェーズフリーの真打ちと言える三機です。
まとめ
1)場所・人・季節ごとに"欠けやすいモノ"を洗い出す
2)定番15品を軸に、家族構成に合わせてカスタマイズ
3)ポータブル電源を組み込んで電気の不安を先回りで潰す
週末キャンプや庭BBQでポータブル電源をわざと空にし、帰宅後にフル充電する——"遊びながら点検"が大事です。遊びと備えをワンセットで回すフェーズフリーな暮らしこそ、いざという時に「無かった」「困った」を言わせない最強の防災術です。
――次の休み、まずはAORA 30 V2に扇風機とLEDランタンをつなぎ、家族で"防災ピクニック"を試してみてください。楽しさの裏側に、揺るぎない安心が宿るはずです。